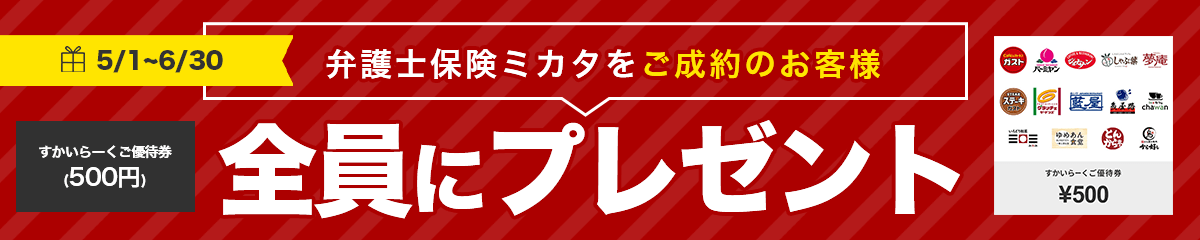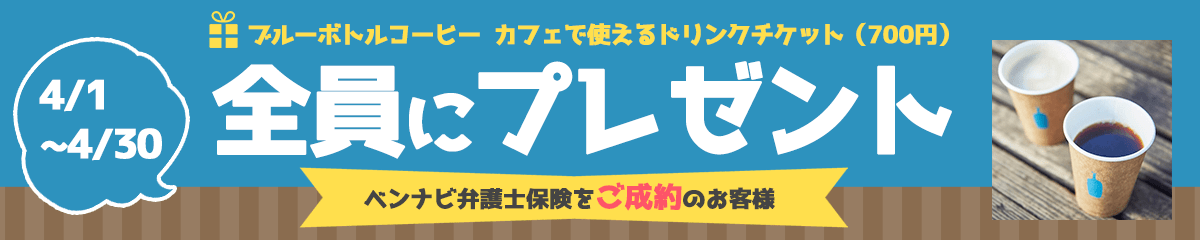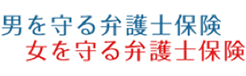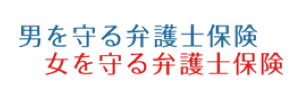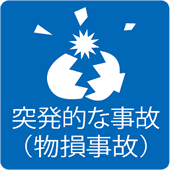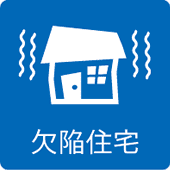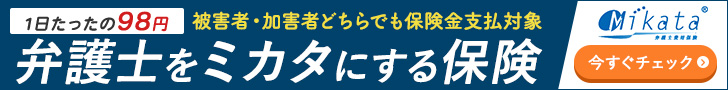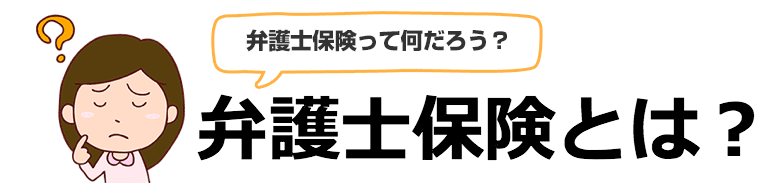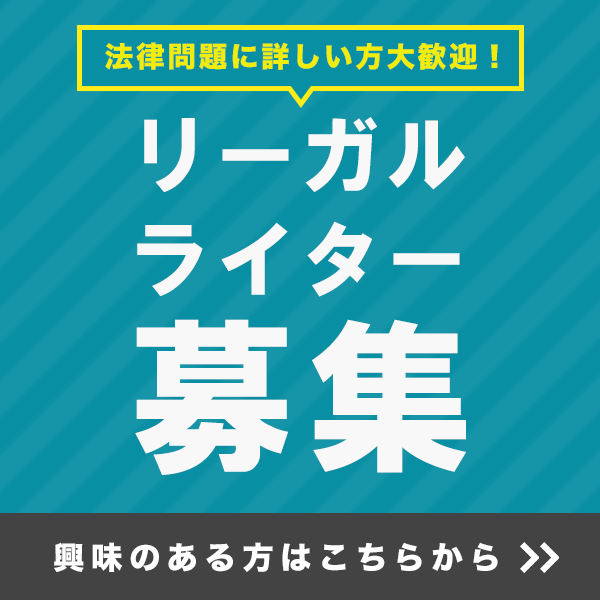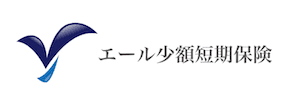離婚が認められる5つの理由とは?証拠集めや慰謝料についても解説
2023年06月12日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人
-150x150.png)
-
2級FP技能士・AFP/金融・法律ライター
離婚や損害賠償に関して調停・本人訴訟の経験あり。
経験と知識を活かし、離婚や交通事故、相続、不動産を中心に多くの記事を執筆。
トラブルには「備え」も重要という考え方から、トラブルの予防・解決に役立つ情報をわかりやすく発信中。
◆WEBサイト
https://visioncapit.com/
最新の投稿
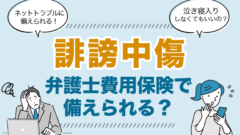 いじめ2024.05.16インターネット上の誹謗中傷は弁護士費用保険で備えられる?注意点や選び方も解説
いじめ2024.05.16インターネット上の誹謗中傷は弁護士費用保険で備えられる?注意点や選び方も解説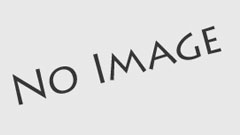 未分類2024.03.28保護中: 【2024年3月最新版】弁護士保険コモンの評判・口コミ
未分類2024.03.28保護中: 【2024年3月最新版】弁護士保険コモンの評判・口コミ 弁護士保険2024.02.29弁護士保険のデメリットは?申し込む前によくチェックしておこう!
弁護士保険2024.02.29弁護士保険のデメリットは?申し込む前によくチェックしておこう!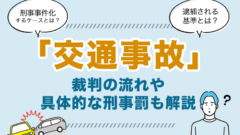 事故2024.02.13交通事故が刑事事件化するケースとは?裁判の流れや具体的な刑事罰も解説
事故2024.02.13交通事故が刑事事件化するケースとは?裁判の流れや具体的な刑事罰も解説
本記事では、離婚したい人または離婚したくない人のために、実際に離婚訴訟(本人訴訟)を経験した筆者が、離婚が認められる理由を解説しています。
有利に解決するために必要な、証拠や慰謝料、財産の把握などの重要性も解説しました。必要に応じて判例も紹介しているので、離婚の可能性がある人はぜひ参考にしてください。
記事の要約
- 民法第770条に定められた5つの理由があれば、離婚が認められる。
- 離婚を請求する側は、離婚原因を立証する必要がある。
- 慰謝料を請求する場合は、離婚原因と慰謝料の額を具体的に主張する必要がある。
離婚が認められる理由とは?
離婚が認められる理由は、離婚を夫婦が決める場合と裁判所が決める場合とでは異なるため、それぞれ分けて解説します。夫婦で離婚や慰謝料の合意ができなければ裁判になる可能性があるため、裁判で離婚が認められる理由も知っておくべきです。
協議と離婚調停では離婚理由は問われない
離婚は夫婦の話し合いで決める(民法第763条)ため、離婚協議や離婚調停では、裁判で離婚が認められない理由であっても、夫婦が合意すれば離婚できます。
離婚協議は裁判所とは関係なく夫婦が離婚について話し合うこと、離婚調停は家庭裁判所で調停委員と呼ばれる人に事情を聴いてもらいながら離婚について話し合うことです。
離婚調停では相手と別の待合室で調停に呼ばれるまで待機しますが、調停の結果話し合いが合意でまとまった場合は、相手との同席を求められることがあります。同席を避けたい場合は、裁判所に相談してください。
裁判離婚には法定離婚原因が必要
協議や調停で離婚の合意ができない場合、離婚するためには裁判が必要です。裁判で離婚が認められる理由(離婚原因)は、次のとおりです。民法第770条第1項)
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
離婚裁判で多くの人が主張するのは、「不貞行為」と「婚姻を継続し難い重大な事由」です。
不貞行為
不貞行為は離婚原因のなかでも代表的なもので、一般的に不倫といわれている行為が該当します。判例では、「自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と説明されています。
性的関係について、「自分は消極的だったけど相手が積極的で断れなかった」ような場合でも、結局は自由な意思で性的関係を結んだので不貞行為です。
いわゆるレイプ(強制性交・強姦)の被害にあった場合は、自由な意思にもとづいて性的関係を結んだわけではないため不貞行為にはなりません。
不倫相手と食事や映画、ドライブデートをした、手をつないだ、キスをした場合は、法律上の不貞行為(性的関係)にはならない可能性があります。ただし、配偶者からの信頼を裏切る行為であり、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる場合もあります。
離婚したい側は、不貞行為の事実を証明するために証拠が必要です。直接的な動画や写真、録音があると離婚が認められやすくなりますが、次のような証拠でも不貞行為があったと認められる可能性があります。
- 不貞相手とのメールやLINE、SNS
- カレンダーのスケジュール
- ホテル予約サイトの予約履歴
- 端末に保存されているWi-Fiの名称(ホテルのWi-Fiなど)
- 不貞相手との通話明細
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
しかし、相手のプライバシーを侵害しないように証拠を得るのは難しいです。証拠が消されてしまう前に、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法第752条)を違反することです。
引用元:最高裁判所「記入例(離婚訴訟)」
病気療養や単身赴任、夫婦仲が悪くなって別居していた場合、家を出て行ったとしても通常は悪意の遺棄と認められません。療養や単身赴任は正当な理由といえ、夫婦仲が悪くなるのは通常お互いのせいだからです。
具体的な判断は裁判所がしますが、ごく一般的にいうと、結婚生活をまったく省みていないと認められる場合に悪意の遺棄と認められる可能性があります。
悪意の遺棄も、証拠が必要です。別居は相手とのやり取りや住民票、生活費を渡さないことは催告をした履歴がわかる相手とのやり取り、通帳などが証拠となります。
3年以上の生死不明
次のような方法をとっても生死不明の状態が3年以上ある場合、裁判で離婚ができます。
- 戸籍の附票から住所や居所を調査して郵便を送ったり、電気メーターの動きや生活観の有無を確認したり、近隣への聞き込みをしたりする
- 親族や勤務先にどこにいるか確認したり、連絡をとってもらったりする
- 警察に捜索をしてもらう
通常は離婚調停をしなければ裁判はできませんが、3年以上生死不明なら離婚調停ができないので、調停をせずに離婚裁判ができます。もちろん証拠が必要なので、3年以上生死不明である証拠を提出しましょう。
- 最後に生死を確認できた日がわかるメール・チャットや手紙、通話履歴
- 戸籍の附票(住所・居所調査)
- 親族や知人、勤務先などの陳述書と証言
- 捜索願の受理証明書
陳述書とは、その人が経験したことや感じたことなどを記載し、裁判の証拠として裁判所に提出する書面です。生死不明についての陳述書は生死不明の証明書面であるため、生死不明者とのやり取りや、探しても見つからなかったといった経緯を記載します。
もっとも、3年以上の生死不明を離婚原因とするのは次の理由から稀です。
- そもそも3年以上生死不明であること自体が稀
- 3年未満であっても生きていることがわかっていれば悪意の遺棄や婚姻を継続し難い重大な事由を離婚原因にできることがある
- 生死不明状態が7年(戦争や災害の場合は1年)以上の場合、死亡したとみなす失踪宣告制度を利用して相続や遺族年金の受け取りができる(民法第30条)以下
3年以上の生死不明を離婚原因とする場合は、弁護士への相談をおすすめします。
回復の見込みがない強度の精神病
相手に統合失調症や認知症など回復の見込みがない強度の精神病があると、裁判で離婚できる可能性があります。
しかし夫婦である以上、相手が病気であっても支えるのが前提です。病気だから見捨てるような形で離婚裁判を起こしても、当然には離婚が認められません。
どのような場合に「回復の見込みがない強度の精神病」を離婚原因として離婚が認められるかというと、誠実に相手を療養し、離婚しても相手は療養に困らない場合が1つの目安です。
相手の実家の資産状態からすると離婚しても療養費に困ることはなく、一方で離婚したい側はお金に余裕がなくても誠実に療養費を支払いながら子どもを育て続け、裁判中も将来の療養費をできるかぎりで支払う意思があると表明したという事情において、離婚を認めた判例があります。
(最判昭和45年11月24日民集24巻12号1943頁)
回復の見込みがない強度の精神病も、悪意の遺棄や3年以上の生死不明と同様に、離婚原因として主張されるケースは多くありません。もし該当しそうな場合は、弁護士への相談をおすすめします。
婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由があると、裁判で離婚できます。不貞行為と同様、離婚裁判でよく主張される離婚原因です。
裁判所は、婚姻を継続し難い重大な事由を次のように説明しています。
引用元:最高裁判所「記入例(離婚訴訟)」
婚姻を継続し難い重大な事由の代表例は、裁判所が示すとおり暴力行為(DV)です。一例ですが、次のような事由は婚姻を継続し難い重大な事由として主張でき、裁判所が離婚を認める可能性があります。
- 慰謝料や財産分与、養育費などの条件は合意していないが、離婚自体はどちらも同意している
- 長期間別居している
- DV(暴力)やモラハラを受けている
- 異常な性行為を要求された
- 性的関係を拒否され続けた
- 相手が性交不能である
- 夫婦生活の継続が困難であるほど著しい性格の不一致がある
- 親族との不仲に起因して夫婦生活の継続が困難となった
- 相手の浪費やギャンブル、借金によって夫婦生活の継続が困難となった
- 相手の過度な宗教活動によって夫婦生活の継続が困難となった
離婚したい側は、自分が主張する「婚姻を継続し難い重大な事由」の証拠が必要です。弁護士に相談するなど、裁判離婚を想定して証拠を集めておきましょう。
離婚が認められる理由がなければ離婚できない?
離婚が認められる理由(離婚原因)がないと裁判では離婚できませんが、夫婦の話し合いでは離婚できます。離婚に合意できず離婚原因もなければ、離婚できません。
どうしても離婚したい場合は、比較的高額の慰謝料や解決金、養育費を支払う約束をすると、相手が離婚を合意しやすくなります。
長期間の別居をして離婚原因を作る方法も考えられますが、相手の反対を押し切ってまで無理に別居したり、別居後生活費を負担すべきなのに負担しなかったりするのは避けましょう。悪意の遺棄にあたり、離婚原因を作った自分の離婚請求が認められない可能性もあるからです。
長期間の別居をしてもなお相手が強く離婚に反対したり、未成熟子がいたり、離婚後相手が経済的に困窮したりする場合には離婚が認められない可能性もあります。
離婚したいが、相手が離婚に合意してくれず離婚原因もない場合にも、弁護士への相談がおすすめです。
離婚が認められる理由がある場合の注意点
離婚が認められる理由がある場合、離婚したい側、離婚したくない側それぞれ注意したいことがあります。それぞれ解説するので、押さえておきましょう。
離婚したい配偶者は証拠集めが重要
離婚したい配偶者は、離婚原因があることを証明しなければなりません。夫婦同士では明らかな事実でも、裁判所は何が真実かを証拠にもとづいて判断する必要があるためです。
LINEでのやり取りやTwitterの投稿、夫婦が書いた日記やメモ、知人の陳述書や証言などを含め、プライバシーを侵害して集めたものなど違法なものでなければ、基本的にどのようなものでも証拠として裁判所に提出できます。
ただし、証拠に対して相手から反論があることも考慮して、できるかぎり「動かぬ証拠」を見つけることが重要です。
離婚が認められる理由を作った側からの離婚請求は認められないことがある
自分が離婚原因を作った場合には、離婚が認められない可能性があります。前述のとおり、未成熟子がいたり、離婚後相手が経済的に困窮したりする場合には、離婚が認められません。
離婚が認められる理由を作った配偶者は慰謝料に注意
離婚が認められる理由(離婚原因)を作った配偶者は、相手から慰謝料を請求されることがあります。一方で、円満離婚のように離婚原因などがないのに相手から慰謝料を請求されることはありません。
一般的には、不貞行為や悪意の遺棄、暴力(DV)をしていた場合に慰謝料を支払う義務があります。もっとも、慰謝料は離婚原因ではなく法律上の不法行為(民法第709条)があったかどうかが問われるものです。不法行為とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為をいいます。
離婚原因がなくても、不法行為をしていれば慰謝料が認められる可能性があるので注意しておきましょう。
離婚前に相手の財産を把握しておく
離婚した後も、慰謝料や財産分与、養育費などで相手とお金の関係が続くことがあります。財産分与とは、基本的には結婚してから別居時までの間に夫婦2人が協力して築いた財産を平等に分けることです。
財産分与では相手が財産を隠すこともあるため、できるだけ相手の預金や株式、投資信託、不動産などの財産を把握しておく必要があります。
相手が慰謝料や財産分与、養育費を支払わなくなった場合も、相手の財産がわかっていれば差押え(強制執行)ができるので財産の把握は重要です。
離婚問題に備えるためには弁護士保険がおすすめ!
離婚問題は、親権や慰謝料、財産分与、養育費、年金分割の問題も絡むなど、お金の面でも精神的な面でも、今後の人生に大きく影響する問題です。
離婚したい場合や離婚したくない場合いずれにしても、自分が望む解決または不利にならないようにするためには、証拠集めや相手との交渉、離婚裁判などで弁護士からのサポートを得ることが強く望まれます。弁護士に依頼するとあなたの代わりに相手とやり取りをしてくれるので、精神的に落ち着くきっかけになる場合もあるでしょう。
しかし、実際に離婚問題に直面しても経済的な理由で弁護士からのサポートを得られず、自分にとって不利な解決となる場合も少なくありません。そこでこのような離婚問題に備えるために、弁護士保険に加入するのがおすすめです。
弁護士保険に加入すると、月額3,000円ほどの保険料で弁護士に相談したり、依頼したりするときにかかるお金を補償してくれます。着手金の相場は30万円ほどなので、加入してからおよそ8~9年は損することなく弁護士に相談や依頼が可能です。
経済的にも精神的にも重要な離婚問題で泣き寝入りすることにならないよう、弁護士保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士保険ステーションは保険会社ではありませんが、あなたに合った弁護士保険選びをサポートするため、4つの弁護士保険を詳しく比較しています。気になる弁護士保険があれば、スマホやパソコンからそのまま申し込み・契約が可能です。
離婚問題に備えるため、ぜひ弁護士保険への加入も検討してみてください。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/