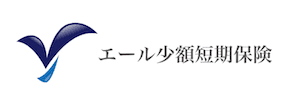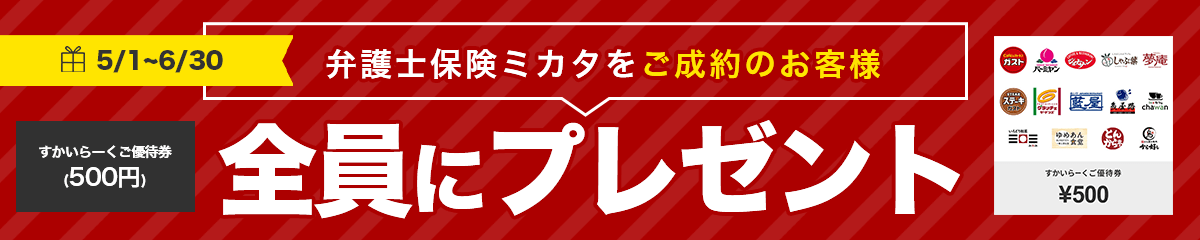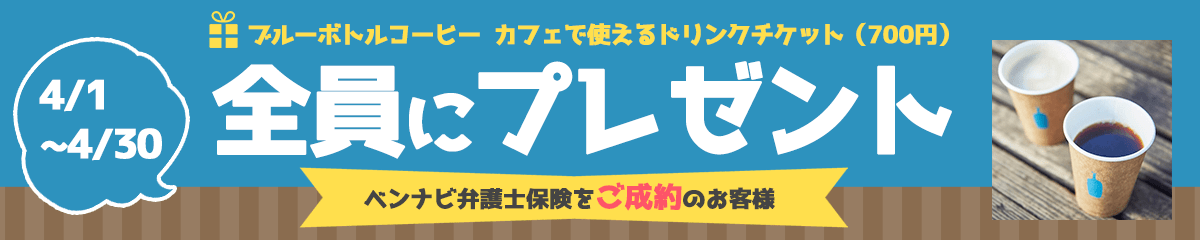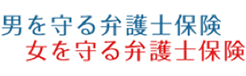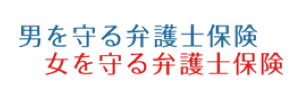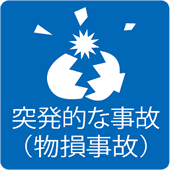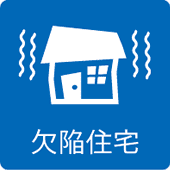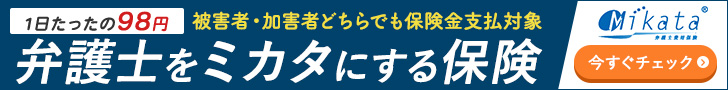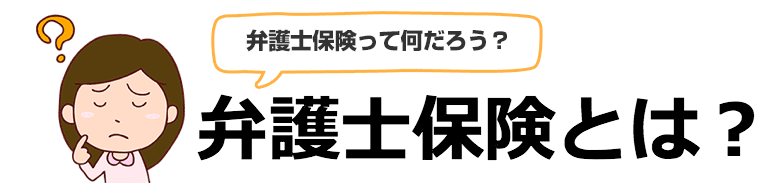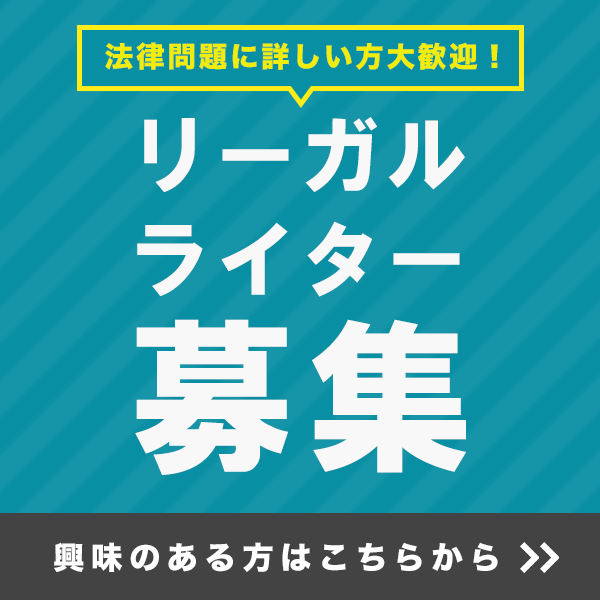誹謗中傷で訴えられた!対策の方法とは
2020年12月3日
▲関連記事をチェック
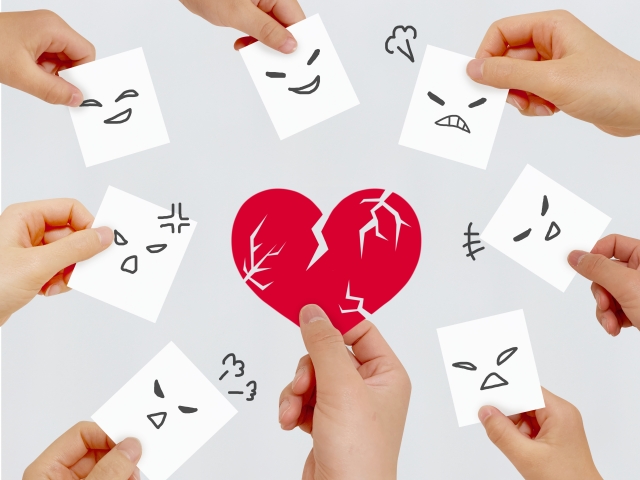
この記事を書いた人

-
弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
最新の投稿
「誹謗中傷」とは、相手を罵り、そしることをいいます。
前提として、誹謗中傷は決してやってはいけないことです。
相手を傷つけ、相手を悲しませることだからです。
ただかっとなってやってしまったり、深く考えずに行動に及んでしまったりする可能性はゼロではありません。
自分が誹謗中傷をした加害者となり、そして被害者側から訴えられた場合はどうしたらよいのでしょうか。
それについて考えていきましょう。
名誉毀損の成立要件について
誹謗中傷によって相手の名誉が毀損された場合、名誉毀損であると判断されることがあります。
ただ、名誉毀損は、「被害者(とされる相手)が訴えれば絶対に認められるもの」ではありません。
たとえば、以下のようなケースでは名誉毀損とは認められません。
公共の利益のための発信
その発言が、多数の人にとって利益となるものであった場合は名誉毀損で訴えられる可能性は極めて低くなります。
たとえば確たる証拠があるなかで、政治家の汚職を取り上げる場合などです。
1対1での話し合いの場合
名誉毀損が認められる要件として、「公然と」というものがあります。
このため、1対1の対面でのけんかのときなどに、相手を誹謗中傷したとしてもそれは名誉毀損にはあたりません。
ただし、インターネットなどで相手の悪口を書き込むなどした場合は名誉毀損にあたります。
事実を適示しなかった場合(ただし侮辱罪に問われることはある)
誹謗中傷に深く関わる罪として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」があります。
この2つは似ているようで違うものです。
名誉毀損罪は「公然と事実を適示して相手の名誉を毀損した場合」に成り立つものであり、侮辱罪は「公然と事実を適示せずに相手を侮辱した場合」に成り立つものです。
たとえば、「あいつは昔人を刺して服役していた」とすれば名誉毀損罪に当たる可能性が高くなりますし、「あいつはバカだ」と罵倒した場合は侮辱罪にあたります。
そのため「誹謗中傷はしたが相手を能無しと罵っただけだ」と主張した場合、名誉毀損罪は認められませんが侮辱罪に問われる可能性があります。
なお、名誉毀損の「事実の適示」は必ずしも「真実」である必要はありません。
その人が実際に服役していた場合でも、また服役していなかった場合でも、名誉毀損罪に問われることがあります。
誹謗中傷を行った場合にとられる対処法と、行動されたときに取るべき対応
誹謗中傷の被害者となった人は、さまざまな対策を行うことになります。
また、そのような対策をとられた場合、加害者としてできることを考えていきましょう。
なおここでは比較的よくみられる、「匿名であることを利用して、軽い気持ちでインターネットで相手を誹謗中傷していた」という場合を例にとりましょう。
相手と自分が知り合いで、かつ相手も自分のことをだれかわかっており、直接連絡がきた
「普段から付き合いのあった人だったけれど、みんなで集まったときの相手の態度が気に食わなくて、ブログで相手を誹謗中傷してしまった」などのようなケースです。
このような場合、相手もあなたのことを知っているため、直接連絡をとってくることもあります。
相手と話し合い、誤解を解いたり謝罪をしたりし、削除をすればそれほど大きな問題にはならないでしょう。
運営者側によってサイトの書き込みが削除される
誹謗中傷をされた被害者は、サイトの運営者に削除要請を出すことができます。
削除要請を受けたサイトの運営者によって、あなたの書き込みが消されることもあります。
またこれは、被害者からの申し出がなかった場合でも、運営者が「悪質だ」と判断した場合には同様の方法がとられます。
削除された場合は、それ以上の書き込みはやめましょう。
削除されたにも関わらず何度も書き込みを繰り返していると、裁判に至る可能性が極めて高くなります。
相手から発信者情報開示請求が届く
誹謗中傷を行った直後ではなく、しばらくしてから情報開示請求などの書類が届く場合があります。
これらは非常に重要な書類です。
この詳細は次の項目で述べますが、情報開示請求が来た場合は決して無視をせず、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
情報開示請求とは? その手順と意味
情報開示請求とは、「相手(加害者・あなた)の個人情報が分からないときに、正当な法的手続きを踏み、相手の情報を明らかにさせるための手続き」をいいます。
相手を誹謗中傷するとき、基本的には自分の立場を明らかにしないで行うことが多いといえます。
インターネットの匿名性を利用し、「自分だということはわからないだろう」と考えて誹謗中傷をするのです。
そのような人に対して被害者が行うのが、「情報開示請求」です。
情報開示請求は、2つの段階を踏んで行われます。
- 1.被害者側が、サイト側などに対して発信者のIPアドレスやタイムスタンプを開示するように請求を行う
- 2.裁判所がサイト側に対して、IPアドレスやタイムスタンプを開示するように言い渡す
- 3.サイト側がIPアドレスやタイムスタンプを開示する
- 4被害者側がプロバイダを特定する
- 5.プロバイダ側に対して、加害者の住所や氏名を開示するように請求する
- 6.裁判所が開示命令を出す
- 7.プロバイダ側から、加害者の住所や氏名が開示される
被害者側は、サイト側とプロバイダ側に対して2回にわたり開示請求を行わなければなりません。
開示請求は個人でもできますが、個人が請求した場合、多くのケースで「プライバシーの保護」を盾に開示請求が却下されます。
そのため被害者側は弁護士を通して開示請求を行うことになります。
このように、情報開示請求には非常に面倒な手順が必要です。また弁護士費用も必要になります。このため多くの被害者はここまですることはしません。
ただ逆をいえば、開示請求の書類が届いた場合は、「相手が本気であり、徹底的に争う構えである可能性が高い」ということです。
速やかに弁護士に相談を! 和解や示談に応じる構えを見せた方が良いこともある
最初に述べたように、「正当性のある書き込み」などの場合は開示請求を受けても戦うことを選択することはできます。
ただし、「匿名で誹謗中傷をしていた」「正当性がないにも関わらず、相手を罵っていた」などのようなケースでは、争うことはおすすめしません。
相手はすでに弁護士に依頼しているため、この段階でこちら側も弁護士に依頼した方がよいでしょう。書き込みの内容によっては、刑事告訴される可能性もあります。
またここで相手からの請求を無視した場合、損害賠償金が大きくなってしまう可能性が極めて高いといえます(なお、ケースによってはいきなり損害賠償請求を受ける可能性もあります)。
民事・刑事、どちらにおいても、「示談が成立しているかどうか」は非常に重要な要件となります。
慰謝料や損害賠償金を適切に支払うことで、刑事事件で起訴される確率も下げることができます。
また相手の訴えに対して真摯に向き合うことで、支払う総額を抑えることも可能です。
いずれにせよ、手元に書類が届いた場合は自分一人で解決しようとせず、弁護士事務所の扉を叩くことをおすすめします。
弁護士は法の知識を持って依頼人を助けますし、また不当な要求から依頼人を守ることもできます。
「加害者側だから、相手の言うことをすべて飲まなければならない」などと思い詰めず、弁護士時に相談するようにしてください。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/