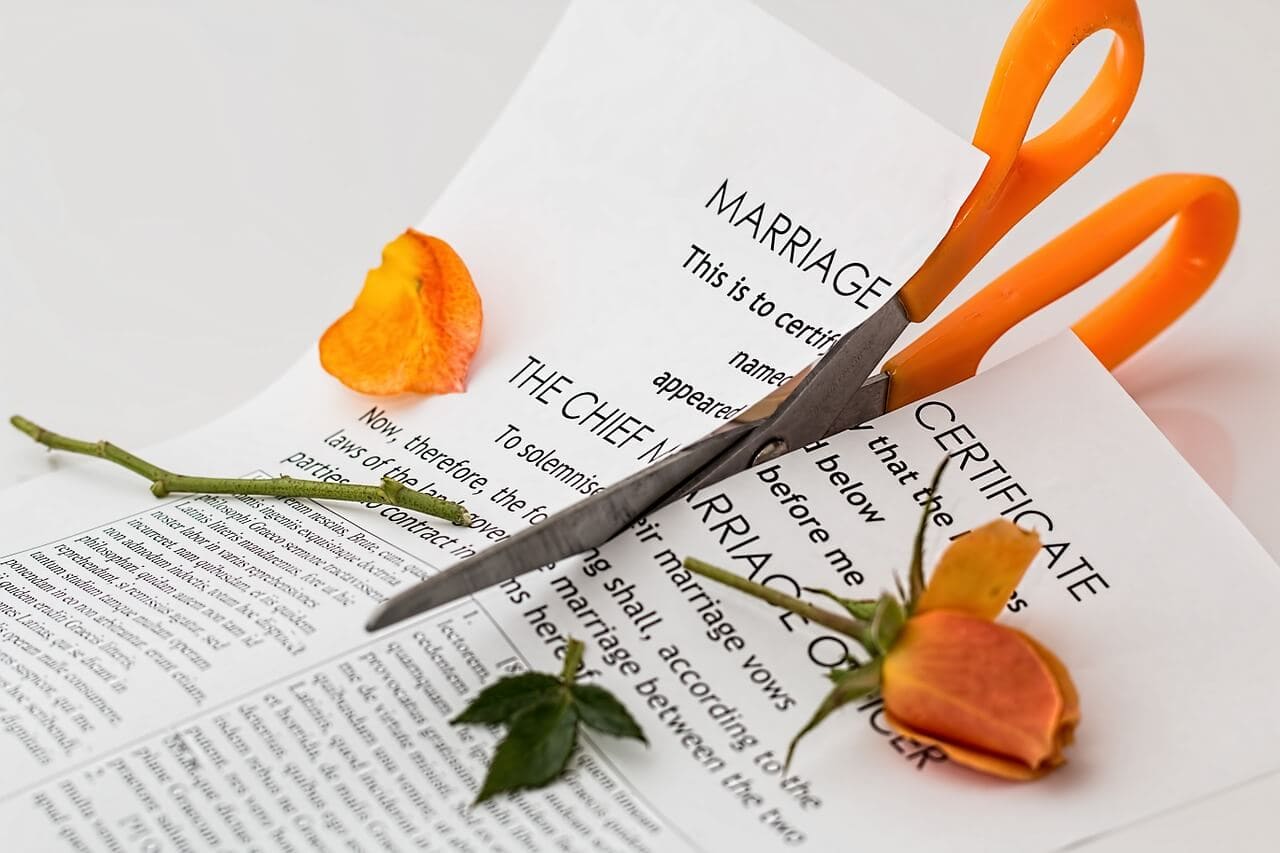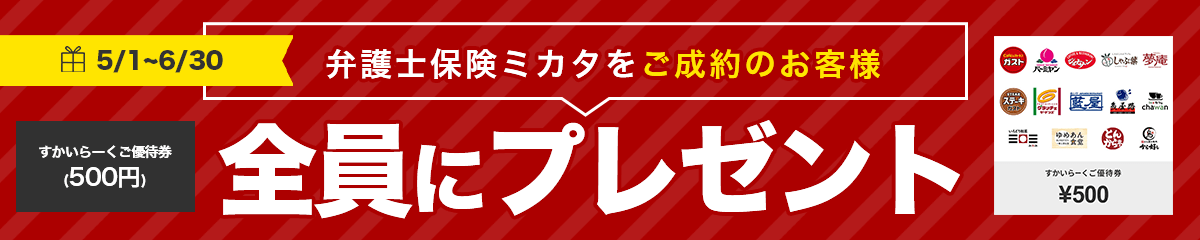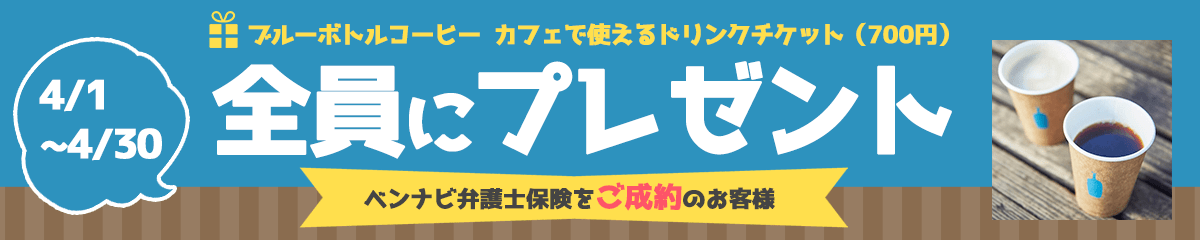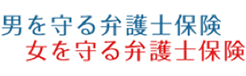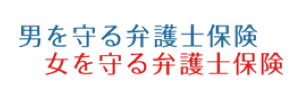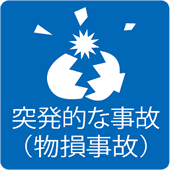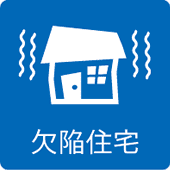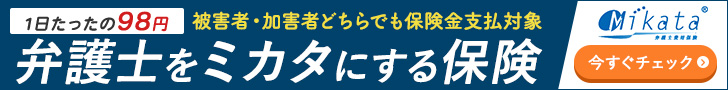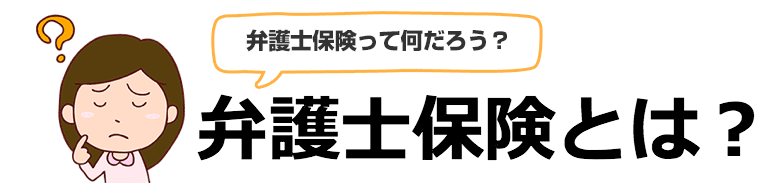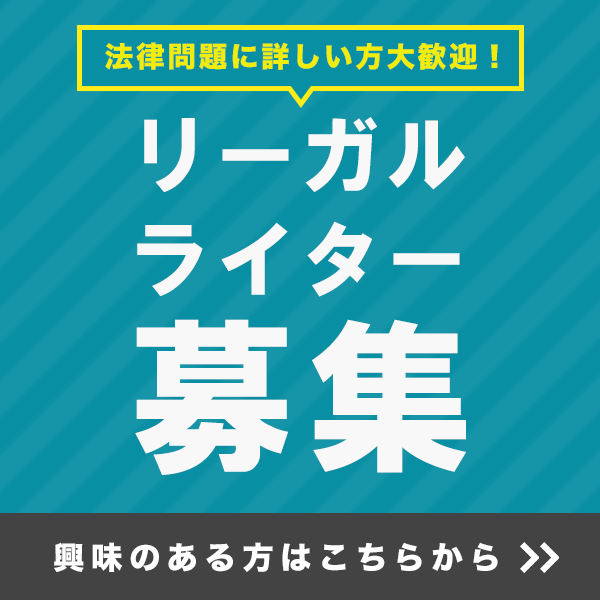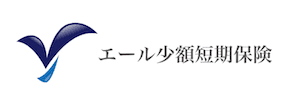離婚の種類について
2018年07月20日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

- 元弁護士
-
京都大学法学部卒。
在学中に司法試験に合格、法律事務所を設立して約10年間弁護士業務に携わる。
その後法律ライターへ転身、法律知識と経験を活かしながら、各種法律メディアや法律事務所サイトで精力的に記事を執筆、監修。
webコンサル業も行っている。
詳細
最新の投稿
 福谷陽子2020.11.11内定取り消しされた!無効になる場合や撤回を求める方法を解説
福谷陽子2020.11.11内定取り消しされた!無効になる場合や撤回を求める方法を解説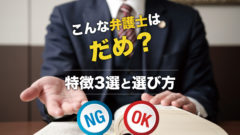 福谷陽子2020.11.09ダメな弁護士の特徴とは?正しい選び方とオススメの探し方
福谷陽子2020.11.09ダメな弁護士の特徴とは?正しい選び方とオススメの探し方 福谷陽子2019.04.09飲食店の自営業者によくあるトラブルと対処法
福谷陽子2019.04.09飲食店の自営業者によくあるトラブルと対処法 福谷陽子2019.04.09専業主婦が離婚したい場合に知っておいた方が良いこと
福谷陽子2019.04.09専業主婦が離婚したい場合に知っておいた方が良いこと
「離婚を進めようと思うけど、まずは何からして良いのかわからない」
「離婚にはいくつかの方法があるって聞いたけど、具体的にはどんな種類があるの?」
離婚するときには、まずは夫婦で協議離婚を進めることが多いですが、実は協議離婚以外にもいろいろな種類があります。
以下では離婚の基本知識として、「離婚の種類」をご紹介します。
離婚の種類一覧
まずは、離婚の種類を一覧で確認します。
●協議離婚
●調停離婚
●審判離婚
●判決離婚
●和解離婚
●認諾離婚
協議離婚、調停離婚以外は聞いたことがない方もおられるかもしれません。以下で、それぞれ説明していきます。
協議離婚
協議離婚は、もっとも一般的な離婚の方法です。日本で離婚する夫婦の約9割は協議離婚の方法で離婚しています。
協議離婚は、夫婦が自分たちで話し合い、離婚に合意して離婚届を役所に提出することによって成立する離婚です。
協議離婚をするときには、市町村役場から「離婚届」の用紙をもらってきて必要事項を書き込み、夫婦がそれぞれ署名押印をして、2名の証人にも署名押印をしてもらいます。
そして完成した離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。
夫婦に未成年の子どもがいる場合に協議離婚をするなら、必ず親権者を決めなければなりませんが、財産分与や慰謝料、養育費などのその他の条件については取り決める必要がありません。
ただ、離婚後のトラブルを避けるためには、必ずこれらの離婚条件についても取り決めをして、離婚公正証書にまとめておくべきです。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の「離婚調停」によって離婚する方法です。
夫婦が自分たちで話合いをしても合意できなかった場合や、そもそも相手と直接話ができないDV事案などで調停が利用されます。日本で離婚する夫婦の9%程度は調停離婚です。
離婚調停をすると、裁判所の「調停委員」が夫婦の間に入って離婚の話合いが進められます。合意ができたら「調停が成立」して、裁判所で調停調書が作成されます。
調停成立後、自宅に調停調書が届くので、それを市町村役場に持って行ったら離婚届を出せます。
審判離婚
審判離婚とは、調停の話し合いを重ねてきたけれど、少しのズレによって離婚できない場合や、最終の期日に一方が出席できなくなった場合などに使われる離婚方法です。
このようなケースでも、調停が不成立になったら夫婦は「離婚訴訟(裁判)」をしなければなりません。しかし、ほとんどの点で合意ができているなら、わざわざ裁判を起こすのは当事者にとっても手間になり、不利益です。そこで裁判所の判断によって離婚させてしまうのです。
ただし審判離婚の決定があったときにも、夫婦のどちらかが異議を出せば効力が失われます。このようなこともあり、審判離婚が行われるのは極めて例外的な事案で非常に少ないです。
判決離婚
判決離婚は、離婚訴訟を起こして判決が出たときに、その判決によって離婚する方法です。
離婚調停をしても合意できずに不成立になってしまった場合には、離婚するために「離婚訴訟」をするしかなくなります。離婚訴訟で最後まで手続きを進めると、裁判所が離婚させるかどうかや、離婚させる場合の条件について決定します。
このようにして「裁判所の判決」で離婚が決まった場合に判決離婚となります。
判決離婚するときには、裁判所から届く「判決書」だけではなく、自分で裁判所に「判決確定証明書」を申請し、判決書と判決確定証明書の2種類の書類を市町村役場に持って行き、離婚届を提出します。
和解離婚
和解離婚とは、離婚訴訟を起こしたけれども途中で夫婦が話合いをして合意し、裁判上の和解によって離婚裁判を終わらせた場合の離婚方法です。
離婚裁判を起こしても、必ずしも最後まで裁判を進める必要はありません。裁判官の仲介によって話合いが進められ、夫婦が離婚することと離婚条件に合意できれば、早期に「和解」によって裁判を終わらせることができるのです。
このようにして和解が成立した場合には、裁判所で「和解調書」が作成されるので、それを市町村役場に持って行ったら離婚届を提出できます。
認諾離婚
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こされたときに、被告(裁判された人)が原告(訴えた人)の請求を全面的に受け入れたときに成立する離婚です。
離婚訴訟を起こされたとき、あえて話合いをするまでもなく「相手の言うことが全部正しいです」と受け入れた場合に認諾離婚が成立します。
認諾離婚の場合、裁判所で認諾調書が作成されるので、それを市町村役場に持って行ったら離婚届ができます。
離婚届の提出期限について

協議離婚の場合の離婚届はいつ提出してもかまいませんが(提出日が離婚日となります)、それ以外の種類の離婚の場合、各手続きの終了後10日以内に市町村役場へ離婚届けをしなければなりません。
調停なら調停成立後10日、判決なら判決確定後10日、和解や認諾の場合には和解日、認諾日のそれぞれ10日以内です。
10日を過ぎても離婚は可能ですが、遅れると「過料」という制裁を科されてしまう可能性があるので、注意が必要です。
離婚には意外といろいろな種類があると感じた方が多かったのではないでしょうか?
対応に迷われたときには、弁護士に相談してみると良いでしょう。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/