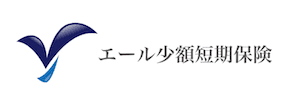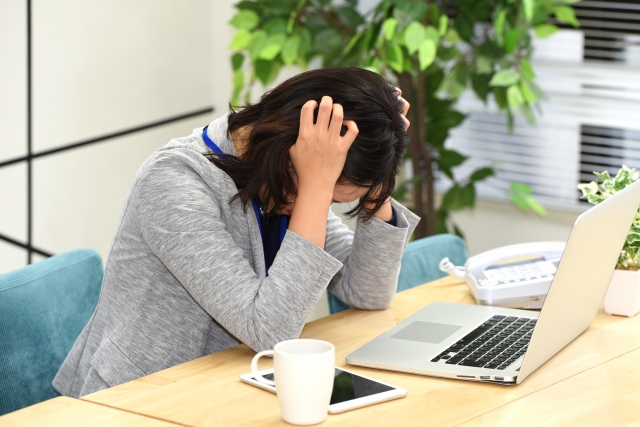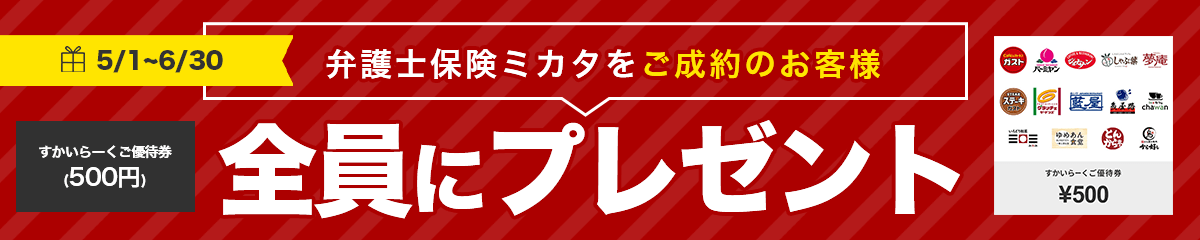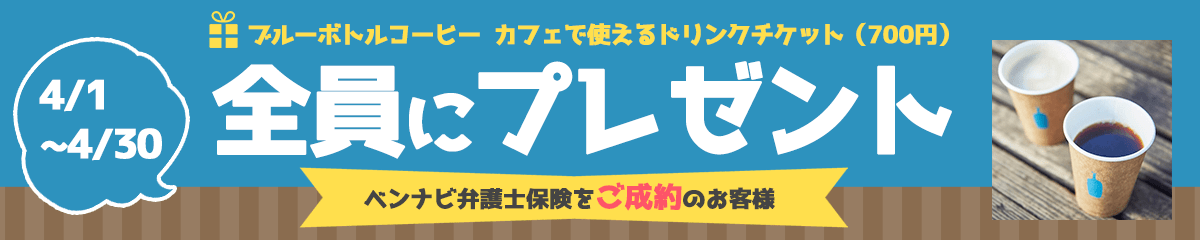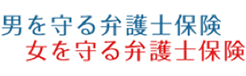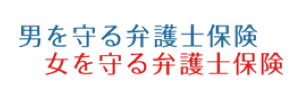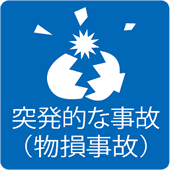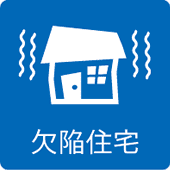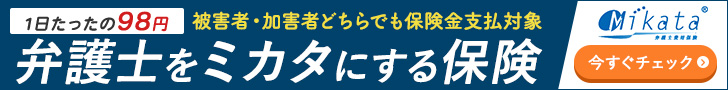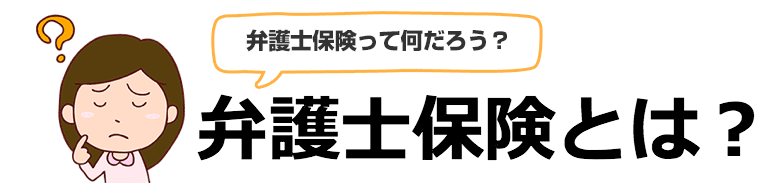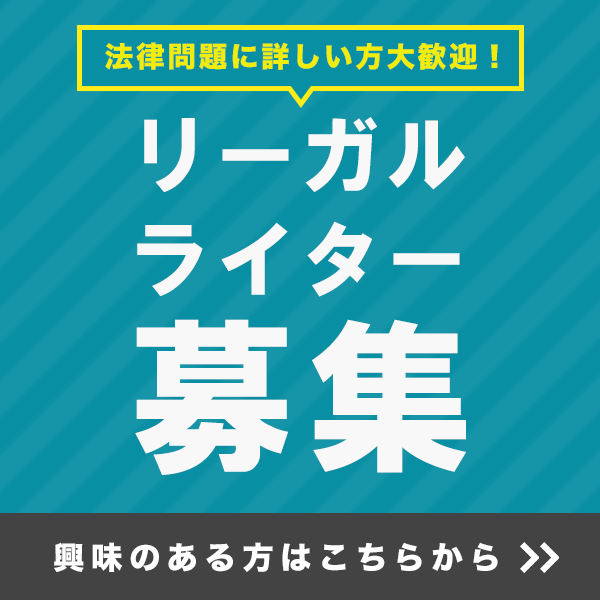従業員からのセクハラ·パワハラ告発!被害者を守るための職場側の対応とは?
2020年04月5日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-
弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
最新の投稿
従業員からのセクハラやパワハラの相談を受けた際に適切な対応ができますか。
対応を誤ると被害の拡大を招く恐れもあり、問題解決には適切な対応が求められます。
セクハラ·パワハラ相談に対する対応方法から、対応時の注意点、再発防止策の取り方まで詳しく紹介します。
従業員からのセクハラ·パワハラ相談に対する適切な対応とは
従業員からのセクハラやパワハラの相談を受けた時はどのように対処すれば良いのか、適切な対応方法について紹介します。
被害者と加害者とされる人物を引き離す
セクハラやパワハラの相談を受けた場合は、まずは相談者の安全を確保することが何より大切になります。セクハラやパワハラの真偽がわからない状態であっても、さらなるトラブルを招かないように相談者と加害者とされる人物が顔を合わさないように隔離しておきましょう。
別の部署や店舗へ異動させ当事者同士が合わないようにするのがベストですが、配置転換では対応できない場合は自宅待機をさせるなどして対処していきましょう。
相談者の話を聞く
まずは相談者の話をじっくり聞いていきましょう。相談者はセクハラやパワハラの被害に遭い気が動転していたり、デリケートな問題の告発に動揺していることもあり冷静に話ができない可能性があります。
そのため、話が飛躍してしまったり、つじつまが合わないことがでてくるかもしれませんが、攻めたてるようなことはせず時間をかけてじっくり話を聞いてあげてください。
相談者が頭の中を整理して話せるように、時系列で話を聞いていくなど話の聞き方を工夫することも大切です。
また、セクハラ問題の場合は、異性には話しづらいこともあるかもしれません。相談者と同性の人物を相談役にするなど、相談者が話しやすいように配慮してあげることが大切です。
可能であれば相談をすべてを録音しておきましょう。
録音を行うときは、必ず相談者の同意を得たうえで行ってください。
調査を行ううえで重要となるメールやLINEなどのやりとりがあれば、コピーをとっておきましょう。
証言とメールやLINEなどのやりとりに矛盾がないか、しっかり確認してください。
加害者に話を聞く
相談者だけでなく、加害者からも話を聞きましょう。
一方の主張を鵜呑みにするのではなく、両者の意見を聞いたうえで総合的に判断していく必要があります。
加害者に話を聞く時も、相談者に話を聞く時と同様に可能であればヒアリングの様子を録音しておきましょう。
メールやLINEなどのやりとりがあればコピーをとり、不自然な点がないか証言と照らし合わせていきましょう。
また、加害者への聴取は、相談者に同意を得たうえで行ってください。
セクハラ·パワハラの有無を判断
両者の言い分を基にセクハラやパワハラが実際に行われていたのか、判断していきます。
ただし、相談者と加害者で言い分が食い違うことも珍しく、両者からの聴取内容だけでは判断が難しいこともあります。
判断が難しい場合は、追加で次のような調査を行っていきましょう。
目撃者に話を聞く
第三者の証言は、事実関係を把握するうえで非常に重要になります。
セクハラやパワハラは密室空間で行われることもあり、該当行為を行っている現場を見た人を探すのは難しいかもしれません。
ただし、実際にセクハラやパワハラが行われている場面でなくても、普段の様子や関係性なども事実認定の判断に役立つこともあります。
社内の人間を中心に、有力な証言がないか第三者にも聞き取りを行っていきましょう。
また、第三者に聞き取りを行う際は、相談者や加害者との関係性も考慮して証言の真偽を見極めていかなければいけません。
相談者や加害者に近しい人物の場合は、示し合わせて嘘の証言を行ったり、親しい人物に肩入れした証言が行われる可能性も考えられます。
聞き取りを行う際は、相談者のプライバシーへの配慮も忘れてはいけません。
相談者のプライバシーが傷つけられることがないように、聞き取りは慎重に行いましょう。
相談者·加害者に再度聞き取り踏査を行う
相談者と加害者の言い分に食い違いがある部分については、当人に再度聞き取り調査を行ってください。
「相手はこのように発言していますが、あなたの認識はどうですか?」と言ったように、ストレートに探って構いません。
再度聞き取りを行った結果、以前の証言と矛盾が生じた場合は発言の信憑性が疑われます。
適正に加害者に対する処分を行う
調査の結果セクハラやパワハラがあったと判断した場合は、加害者に対する処分を検討していきましょう。
処分は軽すぎてもいけませんし、反対に重すぎてもいけません。セクハラ行為やパワハラ行為の内容、頻度などを考慮し、妥当な処分を行ってください。
また、不当に重い処分は無効であると法律で定められています。
処分を巡って訴訟を起こされた場合、処分内容によっては企業側が敗訴する可能性があるので注意してください。
セクハラ·パワハラの再発防止に努めよう
セクハラやパワハラの問題は調査を行って終了ではありません。
今後同じような問題が起こらないように、再発防止策を講じていかなければいけません。
そもそも企業は社員が働きやすい労働環境をつくる義務を負っています。
社員が快適に働けるように、しっかり責任を果たしていきましょう。
具体的な再発防止策を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
企業方針の周知
会社としてセクハラやパワハラを禁止していることを、日頃から社員に示しておきましょう。
しっかり会社の方針を周知しておくことが、セクハラやパワハラの防止につながります。
また、セクハラやパワハラを行った場合には、厳正に処分することも併せて周知しておくと良いでしょう。
朝礼などを通じて、定期的に発信を行っていきましょう。
就業規則の整備
セクハラやパワハラの禁止や、処分については就業規則にも明記しておきましょう。
就業規則は社内の規律や労働条件を定めたものであり、社員に社内の方針を周知させ同じ認識を共有するのに有効です。
相談窓口の設置
トラブルが発生したときに、いつでも社員が相談を行えるように相談窓口を設置しておきましょう。
また、相談窓口が設置されている旨を、社員に伝えることも大切です。
セクハラやパワハラの被害にあっても相談先がわからず悩んでいる社員がいるようでは、相談窓口を設置していても十分な対策を講じているとは言えません。
相談を受ける体制の整備
セクハラやパワハラが起こったときに適切な対応ができるよう、相談を受ける体制を整備しておく必要があります。
事実関係の調査方法や処分の判断基準など相談から問題の解決まで、どのような手順で対応を進めていくのかあらかじめ決めておきましょう。
マニュアルなども用意しておくと良いでしょう。
また、スムーズに相談対応を行えるよう、必要に応じて担当者の教育も実施してください。
相談者を守る体制づくり
パワハラやセクハラは非常にデリケートな問題であり、相談窓口を設置してもプライバシーが守られる保証がなければ相談に踏み出せない人もいるでしょう。
そのため、相談者のプライバシーを守る体制づくりを行うとともに、相談者のプライバシーはしっかり守ることを社内に周知していく必要があります。
また、自分より上の立場の人間からセクハラやパワハラを受けている場合は、告発することにより不利益な扱いを受けるのではないかと不安を抱き相談に踏み出せない人もいるでしょう。
不安を抱えず安心して相談できるように、プライバシーや利益を保護し相談者を守る体制を整えていきましょう。
セクハラ·パワハラ相談を受ける際の注意点
セクハラやパワハラ相談を受ける際は、相談者を傷つけることがないように言動には十分に注意しなければいけません。また、相談を蔑ろにせず、誠意ある対応を心がけることも大切です。
セカンドハラスメントに気をつける
セクハラやパワハラの相談を受ける際は、セカンドハラスメントを起こさないように言動には十分注意しなければいけません。
セカンドハラスメントとは、ハラスメントの二次被害のことです。
被害者である相談者を責めたり被害を軽視する言動がセカンドハラスメントを引き起こす原因で、ただでさえ苦しんでいる相談者を余計に傷つけてしまいます。
悪気はなくても無意識のうちに相手を傷つけることになるので注意しましょう。
次のような発言は、セカンドハラスメントを引き起こす可能性が高くなっています。
- なんでやめてと言わなかったのと攻める
- あなたにも問題があるのではと疑う
- 気にしすぎじゃないのと被害を軽視する など
適切な調査を行う
企業がセクハラやパワハラの相談を受けた場合は、適切に対応することが義務付けられています。
相談を受けたにも関わらず対処を行わなかった場合は、義務を怠ったとして会社に対して慰謝料請求が行われる恐れがあるので注意してください。
また、十分な調査を行わず形式的な調査だけで問題の対応を済ませた場合も、不適切な対応とみなされ慰謝料請求が行われることがあります。
過去にはセクハラ問題において事実確認を簡単に済ませ、加害者に対しても軽い注意しか行わなかった企業に対して裁判所が損害賠償を命じた事例もあります。
セクハラやパワハラ問題は蔑ろに扱ってしまうと、企業もいつの間にか加害者になってしまう恐れがあるので対応にはくれぐれも気をつけましょう。
解決が難しい時は弁護士に相談を
セクハラやパワハラの問題は、簡単に解決できるものではありません。
対応を誤ると相談者を余計に傷つけてしまったり、さらなる被害の拡大を招く恐れがあります。
また、加害者に対する処分も難しく、不当に重い処分を与えると裁判を起こされ処分が無効となるリスクも潜んでいます。
さらに対応が後手に回ると、どんどん大きなトラブルに発展してしまうこともあります。円滑に問題を解決するには、弁護士の手を借りるのも一つの手です。
労働トラブルに精通している弁護士に依頼すれば、適切な対応でスピーディーに問題を解決してくれるでしょう。
トラブル解決だけでなく再発防止対策についても相談を行うことも可能となっており、問題解決に向けて全面的なバックアップを受けられます。
万が一に備えて弁護士保険を活用しよう
トラブルの解決には法律の専門家である弁護士の力を借りるのが一番ですが、弁護士に依頼するとなるとどうしても高額な費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士保険に加入しておけば、費用の問題も心配いりません。弁護士保険とは、弁護士に依頼を行った際に必要となる法務費用を補填してくれる保険です。
弁護士保険に加入していれば万が一のトラブルに見舞われても費用を気にせず、すぐに弁護士を頼ることができます。
補填内容や会社によって毎月の保険料は変わってきますが、月7,000円程度から加入できる保険もあります。
顧問弁護士を雇うほどの余裕はないが、弁護士を活用したいという企業の方は弁護士保険に加入してみてはいかがでしょうか。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/