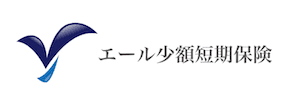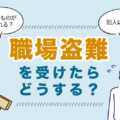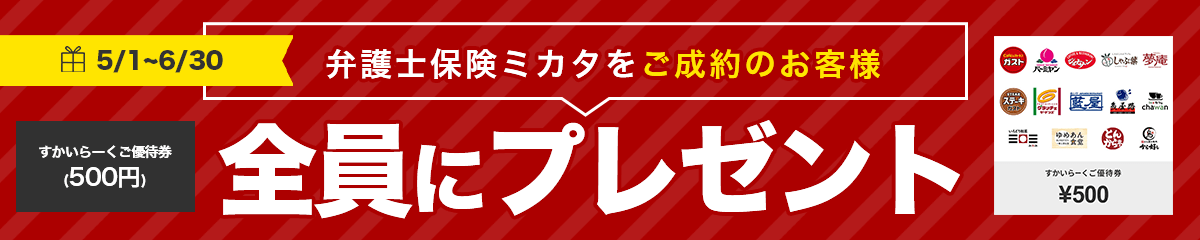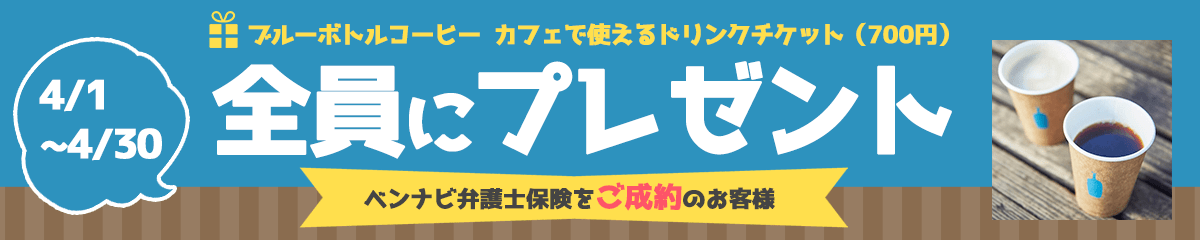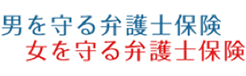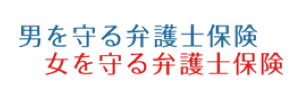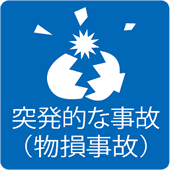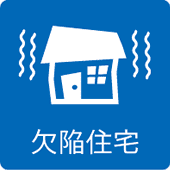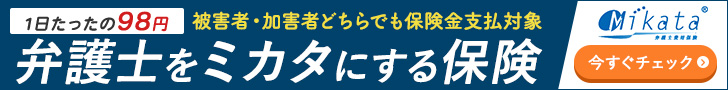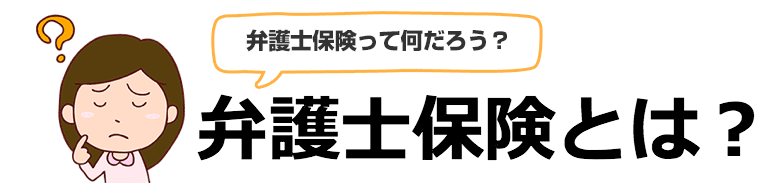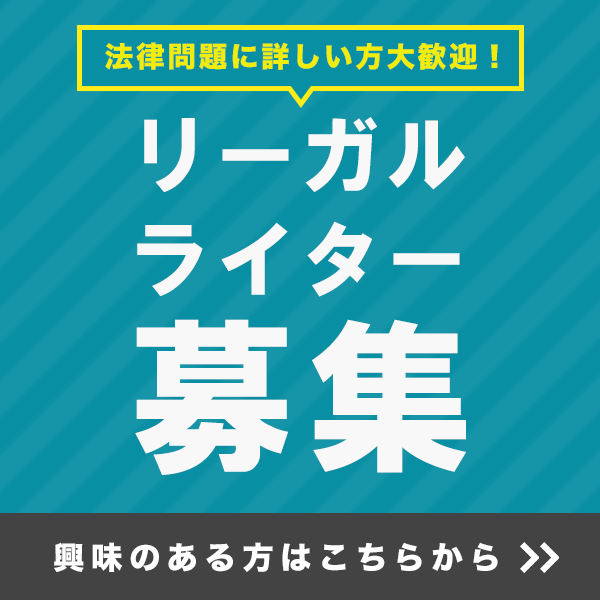従業員からいじめ被害の相談をされたら?被害者を守るための職場側の対応とは?
2020年04月7日
▲関連記事をチェック
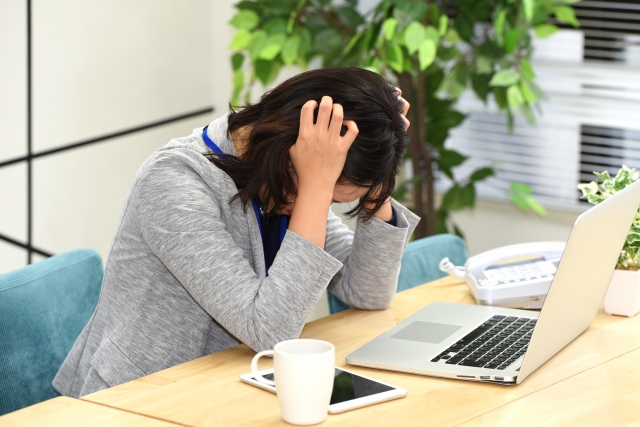
この記事を書いた人

-
弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
最新の投稿
社員からいじめの相談を受けたら適切な対応ができますか。
いじめというデリケートな問題の対応は、簡単ものではありません。
また、誤った対応を行ってしまうと、相談者をさらに傷つけることになりかねません。
適切に社内のいじめ問題を解決できるよう、相談を受けた際の対応方法について紹介します。
社員からのいじめ相談に対する適切な対応とは
社員からいじめの相談を受けた場合は、相談者のプライバシーを守りながら適切に対処していく必要があります。
対応を誤ると相談者をより傷つけてしまう恐れもあるので、慎重に対応を行っていきましょう。
誤った対応をすることがないように、いじめ相談を受けた際の適切な対処法を確認していきましょう。
相談者を安心させる
まずは本題に入る前に、相談者が話しやすい空気を作ってあげることが大切です。
いじめはナイーブな問題であり、相談者は不安や緊張を抱えながら相談に来るケースも珍しくありません。
簡単な自己紹介をするなどして、相談者の緊張をほぐしてあげましょう。
相談者が不安がなく話せるように、相談者のプライバシーはしっかり守ると伝えてあげることも大切です。
いじめの相談をしたことが予期せぬ形で社内に広まってしまうと、相談者を余計に傷つけてしまう恐れがあります。
プライバシーの保護は徹底して行っていきましょう。
また、相談に対して確実に対応することを確約しましょう。
相談を聞くだけでは、適切な対応が行われるのか相談者も不安になってしまいます。
事実確認
次にいじめの事実が本当にあるのか、事実確認を行っていきます。
「いつ」「どこで」「誰に」「どんないじめを受けたのか」詳しく聞いていきましょう。
ただし、相談者の意見をしっかり聞くことは大切ですが、言っていることを全て鵜呑みにするのは危険です。
例えば、一方は指導のつもりでも、一方はいじめと受けとめているというように両者で言い分が大きく異なるケースもあります。
相談者だけでなく、加害者とされる人物や現場を目撃していそうな第三者にヒアリングを行っていきましょう。
ただし、本当にいじめが行われている場合、いじめを告発されたことが引き金になり余計にいじめがひどくなることも考えられます。
相談者を守るためにも、加害者とされる人物のヒアリングは慎重に行いましょう。
また、ヒアリングは中立的な立場の人物が行ってください。
どちらか一方と親しい人物がヒアリングを行うと親しい人物に肩入れしてしまい、公平にヒアリングが行われない恐れがあります。
事実確認を基に対応
事実確認を基に、いじめの有無を判断します。いじめと認定できた場合と、いじめとは認定されなかった場合で対応は異なってきます。
いじめの事実が認定できた場合
いじめの事実が認定ができた場合は相談者に調査結果を報告するとともに、しっかりケアを行っていきましょう。
いじめの影響で精神状態に異常をきたしている場合は、普通の精神状態に戻れるようにケアしなければいけません。
また、いじめが原因で退職してしまった場合は、復職できるよう支援していかなければいけません。ケースによっては慰謝料の支払いが必要になることもあります。
加害者に対しては懲戒規則や就業規則に則って適切な対処を行っていきましょう。
ただし、不当に重い処分を下してしまうと、訴訟を起こされるなどさらなるトラブルを招きかねません。
また、処分が不当と判断された場合は、処分が無効になってしまうという点も頭に入れておかなければいけません。
自分たちだけでは処分の判断が難しい場合は、弁護士など専門家の力を借りて適正な判断を行ってください。
いじめの事実が認定できない場合
いじめの事実が認定できなかった場合でも、相談者に対してしっかりケアを行うことが大切です。
いじめは認められなかったと結果だけを伝えて突き放すのではなく、なぜいじめと認定され中なかったのか理由も説明することが大切です。
いじめの事実はなくても、相談に来たということは相談者が相当悩んでいたのは明白です。
相談者の悩みが解決できるような判断に至った理由や経緯をしっかり説明してあげましょう。
必要に応じて部署異動や定期的な面談を実施するなど、相談者が働きやすい環境を作ってあげることも大切です。
行為者に対しては調査結果を伝えるとともに、今後トラブルが起きないように話し合いを行いましょう。
いじめと認定されなくても、行為者の行為を不快に感じていた人がいるのは事実です。
今後も同じようなトルブルを引き起こさないために、
「どのような行為が誤解を招いてしまったのか」「誤解を生まないために今後どうするべきなのか」しっかり話し合いましょう。
いじめ防止の対策を行う
いじめ問題が解決したら、今後同じような問題が起こらないように対策を行っていくことが大切です。
社内ルールを見直すとともに、再発防止の研修などを行い徹底して注意喚起を行っていきましょう。
大ごとになる前に問題を解決できるよう、気軽に相談できる窓口などの設置も有効です。
また、必要に応じて定期的にヒアリングやアンケートなどを行い、職場の実態把握にも努めていきましょう。
いじめを立証するためには証拠が重要
いじめの有無は、両者の証言だけでは判断しづらい面があります。
そこで重要となるのが、証拠です。いじめ問題に対応する際は、客観的に見てどちらの言い分が正しいのかわかるような「証拠」集めも必要です。
どのようなものが証拠として有効になるのか、見ていきましょう。
目撃証言
第三者の目撃証言は有効な証拠です。
社内やお店の中など多くの人が集まる場所での出来事ならば、誰かしらは目撃している可能性が高くなっています。
社員や店員など第三者に聞き取りを行い、目撃証言を集めましょう。また、ヒアリングを行う際は、当事者との関係を十分に考慮することが大切です。
当事者と親しい人物の場合、当事者をかばうような発言をしたり、当事者と示し合わせて嘘の証言を行う可能性もあります。
当事者と近しい関係にある人物にヒアリングを行う際は、目撃証言を集めていると悟られないように直接的な質問は避けるようにするのがベストです。
録音した音声データ·録画した映像データ·写真
録音した音声や録画した映像、写真も有効な証拠です。
近年ではボイスレコーダーやスマートフォンを使って簡単に録音や録画が行えるようになっていおり、相談者が既に証拠としてデータを記録していることもあります。
また、相談時点ではデータを記録していなかったとしても、日常的にいじめが行われている場合はすぐにデータを録って証拠として押さえることができます。
もちろん防犯カメラなどの映像も有効な証拠です。
診断書
いじめが原因で精神や身体に異常をきたした場合は、病院に行き診断書を発行してもらいましょう。
診断書は被害の大きさを表す、重要な証拠です。
ただし、診断書だけではいじめとの因果関係が認められないこともあります。
音声データや映像データなど他の証拠と併せれば、診断書の証拠としての有効性が高まります。
メモ·日記
いじめの事実を記録したメモや日記も証拠として有効です。
ただし、曖昧な内容では証拠としては弱くなってしまいます。
内容が詳細であればあるほど有効性は高まります。
日時や場所、どのようないじめを受けたかなど具体的な内容が記されていると良いでしょう。
被害者のプライバシーを傷つけない対応を行おう
いじめ問題は非常にデリケートな問題です。
そのため、被害者のプライバシーを傷つけないように、慎重に対応を行わなければいけません。
ヒアリングを行う場合は人目につかない場所を選び、情報が漏れないように気をつけましょう。
また、自分一人では解決が難しく上司や弁護士に相談を行う際は、情報を共有しても問題ないか必ず相談者に確認を行ってください。
情報を知っている人数が増えるに連れて社内に情報が広まる可能性が増え、思わぬ形で加害者とされる人物の耳にとどてしまうことがあります。
相談者のプライバシーを守るために、情報の取り扱いにはくれぐれも注意しましょう。
いじめ相談の放置はリスクが高い
いじめ問題はケースによっては会社や個人の信用問題にもつながる、非常にデリケートな問題です。
対応も難しく問題を投げ出してしまいたいと思うこともあるかもしれませんが、問題を放置するのは大変危険です。
いじめ問題に対処しなかった場合に考えられるリスクについて紹介します。
慰謝料請求を行われる
いじめにより精神的な苦痛や肉体的な苦痛を受けた場合に、被害者が慰謝料請求を行うことがあります。
加害者に対して慰謝料請求を行うことはご存じの方も多いでしょうが、慰謝料請求を行う相手は加害者に限らないということはご存じではない方も多いのではないでしょうか。
上司は職場の秩序を守るために部下の行動を監視·監督する義務があり、義務を怠った場合は慰謝料を請求される可能性があります。
つまり、いじめの相談を受けたにも関わらず問題を放置してしまうと監督義務を怠ったとみなされ、自分にも慰謝料請求が及ぶということは頭にいれておかなければいけません。
人事評価に影響を与える
問題を放置した事実が明るみに出ると、自身の評価に影響を与える可能性があります。
降格や減給の恐れもあるので、注意が必要です。
相談を受けた当人だけで問題を解決する必要はないので一人で問題を抱え込まず、必要に応じて上司や社長に相談を行い問題解決に努めていきましょう。
解決が難しい場合は弁護士に相談を
いじめ問題は、弁護士など専門家抜きには解決が難しいケースが多くなっています。
相談者と加害者とされる人物で意見が食い違うことも珍しくなく、事実関係を調査するだけでもかなりの時間と労力が必要です。
さらに、いじめと認められるかの判断基準も難しく、素人だけで解決するのは至難の業です。
加害者への処分も頭を悩ます問題で、不当な処分を行なうと今度は加害者から会社が訴えられてしまうこともあります。
自分たちでは解決が難しい場合は、労働トラブルに強い弁護士に頼るのが一番です。
経験と実績を生かし、スムーズに問題を解決へ導いてくれます。また、当事者もプロによって行われた判断の方が、納得して受け入れることができるでしょう。
問題の解決が難しい場合は社内で問題を抱え込まず、弁護士に相談してみましょう。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/