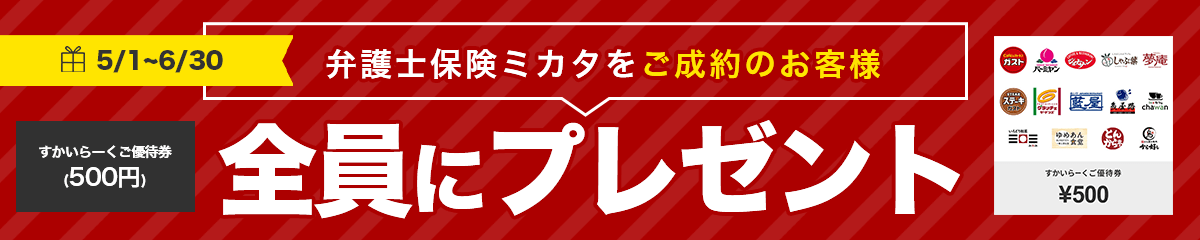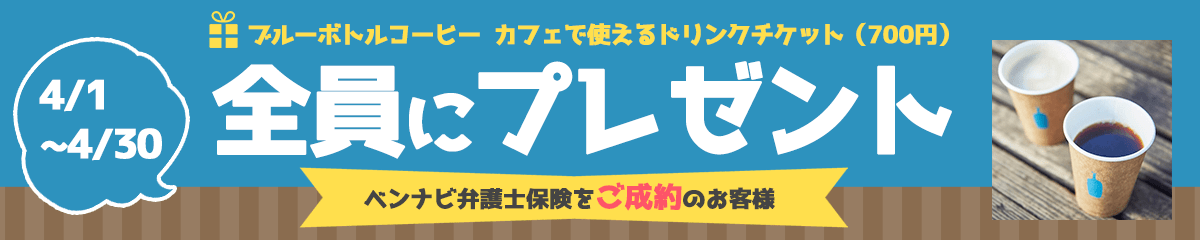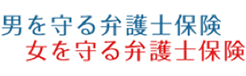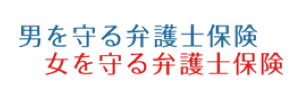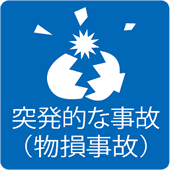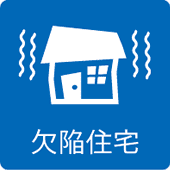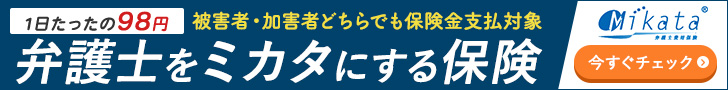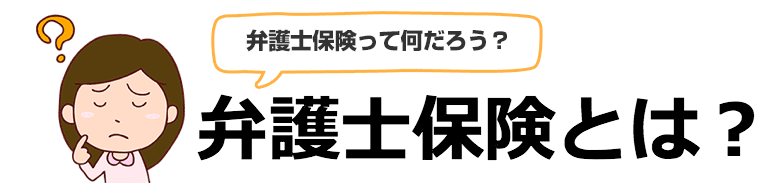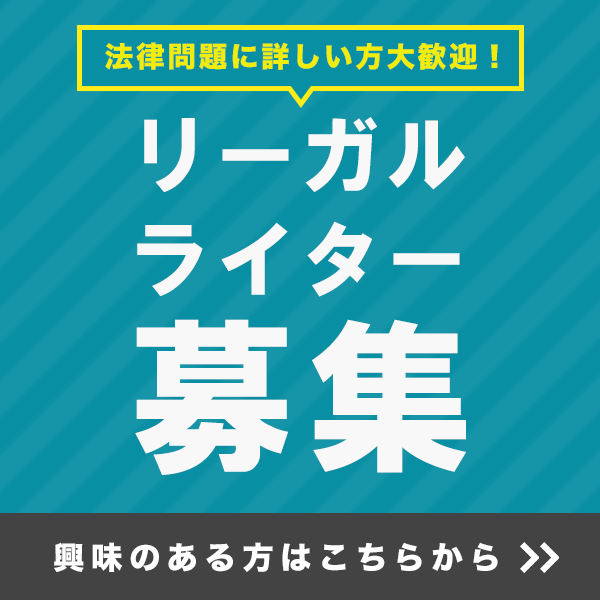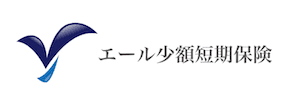遺産相続の相続順位と相続割合をわかりやすく解説!
2021年11月26日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-
2級FP技能士
金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。
◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ
最新の投稿
 トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例
トラブル2023.05.24美容師の退職、トラブルを回避するための5つの方法とは?伝え方や判例 トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法
トラブル2023.05.19YouTuberの動画投稿をきっかけとした「個人情報流出トラブル」の事例と対処法 賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説
賃貸2023.03.14マンション・アパートの引っ越し挨拶はどこまで?賃貸も必要?おすすめの手土産も解説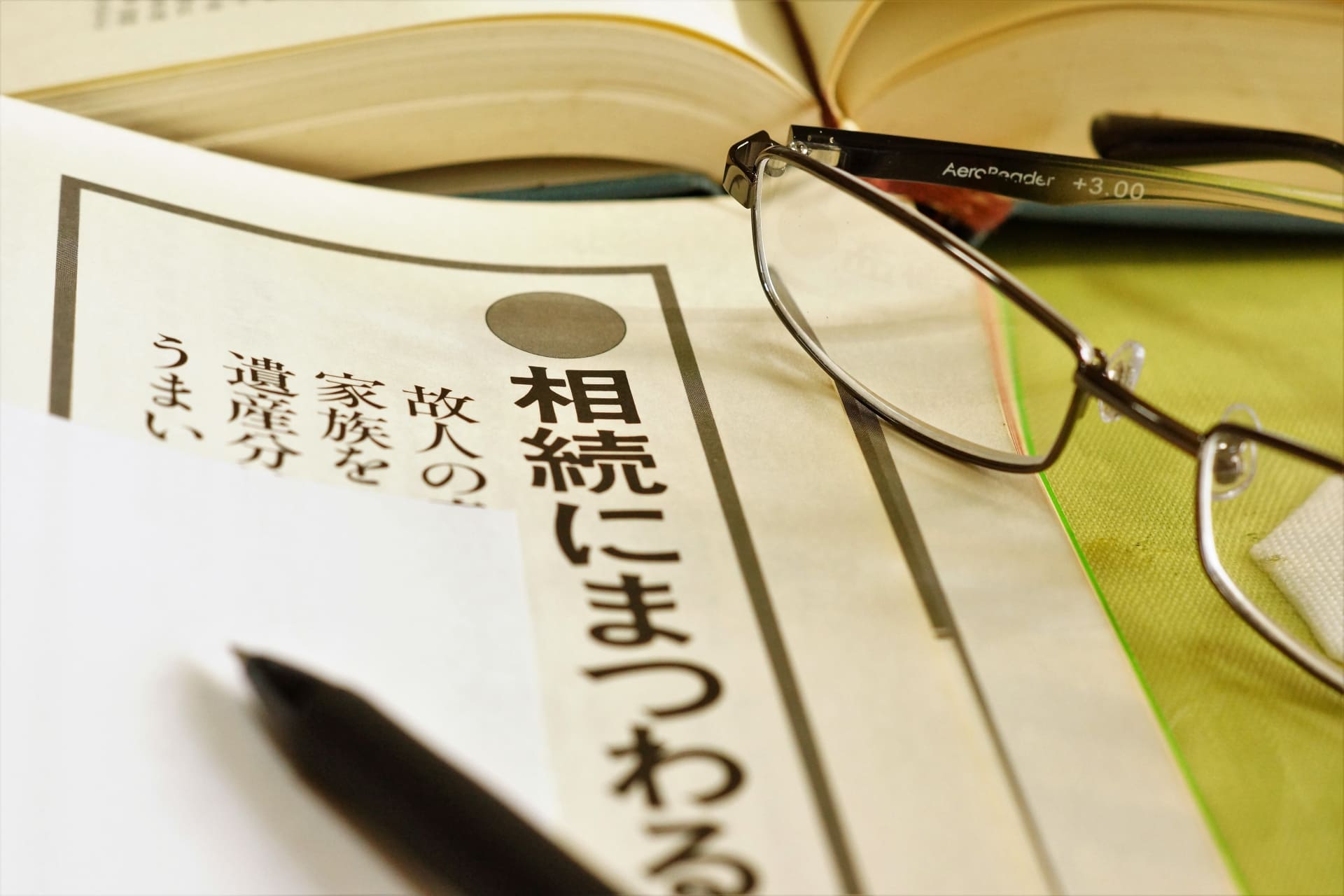 相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで
相続2023.02.21<FP解説>遺留分とは?意味や相続分との違いから範囲や時効・計算シミュレーションまで
遺産相続は遺言書や遺産分割協議によって相続する人や割合・方法などを決定します。
遺言書がある時には基本的には遺言書通りに、遺言書が無い場合は遺産分割協議において相続人全員で話し合います。
ただし遺族の生活の保障や相続人同士のトラブルを回避するために、民法上でも相続割合や順位が定められています。話がまとまらない時、調停・裁判に発展した時に「法定相続分」が重要な役割を果たします。
相続の順位・割合はどうやって決めるのでしょうか?
民法での相続順位や割合はどうなっているのでしょうか?
本記事では法律で定められた相続の順位・割合や遺産分配の決定方法、9つのケース別の相続順位・割合を解説していきます。
相続の予定がある方、知りたい方はぜひご参考になさってください。
記事の要約
- 遺産相続は遺言書または遺産分割協議で決定する。
- 法定相続分は相続人間の合意がない場合の基準。
- 特殊ケース(代襲相続、胎児、非嫡出子)で相続順位・割合が変動する。
- 相続放棄時、放棄者は初めから非相続人とみなされる。
- 相続人不在時、財産は国庫に帰属し、特別縁故者に分与されることもある。
相続の順位と割合は「法定相続分」で定められている
民法では相続時の遺産分割において、相続の順位・割合を以下のように定めています。
| 相続順位 | 法定相続分 | 遺留分※2 (法定相続分の1/2) |
||
|---|---|---|---|---|
| 常に相続人となる 配偶者 |
第一順位 | 子供・孫などの直系卑属 | 配偶者:1/2 直系卑属:1/2※1 |
○ 配偶者:1/4 直系卑属:1/4 |
| 第二順位 | 父母・祖父母など直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
○ 配偶者:1/3 直系尊属:1/6 |
|
| 第三順位 | 兄弟姉妹 亡くなっている場合は甥・姪 |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
× 配偶者:3/8 兄弟姉妹:なし |
|
※1.第一順位~第三順位の方が2人以上の時は全員で1/2
※2.遺留分とは遺族に定められた最低限の取り分を指します。
法定相続分は相続人の間で遺産分割について意見がまとまらなかった場合の取り分ですので、相続人全員で合意が得られている場合には上記の相続分通りではなくても大丈夫です。
なお配偶者は法的に婚姻関係にある人を指しますので、内縁関係の方は含まれません。
法定相続分や遺言書・遺産分割協議など様々な判断材料がありますが、実際に相続の割合や分配はどうやって決めるのでしょうか?
遺産の分配:遺言書と遺産分割協議はどちらが優先される?
遺産の相続人や割合は、遺言書がある場合には基本的に遺言書通りの内容、遺言書が無い場合には遺産分割協議で決定する流れとなります。
遺言書は故人の意向を記した重要な書類ですので、遺言書がある時には従う事が望ましいとされています。ただし下記3つのケースでは遺産分割協議で決定した方が良い可能性が高いです。
被相続人の直系尊属(父母など)と直系卑属(子供など)に定められている「遺留分」を侵害しているケース。ただし侵害されている方を含め相続人全員の合意が得られている時には可能。
2. 相続人・受遺者※の全員が合意している
遺産分割協議で相続人・受遺者の全員が合意している時には、必ずしも遺言書通りに相続する必要はありません。
3. 民法上の相続財産ではないものを指定している
死亡退職金・死亡保険金など「みなし相続財産」と呼ばれ、民法上相続財産ではないものの遺産相続の指定は無効とされています。
※受遺者とは法律上相続人ではないものの、遺産を受け取る人のことを言い被相続人が生前お世話になった人などが挙げられます。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、意見をまとめた後内容を「遺産分割協議書」として作成します。相続人が一人でも欠けていると無効となり、全員の合意を得られないと協議書を作成できません。
遺産分割協議書は後の相続手続きで必要な書類となりますので、遺産分割協議の際には全員の意見がまとまるまでよく話し合いましょう。
相続放棄・代襲相続…どうする?9つのケース別の相続順位・割合
代襲相続や相続人の中に胎児がいるなど9つのケース別における相続順位・割合を解説していきます。
- 代襲相続の場合
- 代襲相続人が亡くなっている
- 配偶者がいない又は亡くなっている
- 身分関係が重複している
- 相続人の中に胎児・非嫡出子がいる
- 相続放棄がある時
- 相続人がいない
- 相続人の中に養子がいるとき
- 相続廃除・欠格となる場合
1.代襲相続の場合
第一~第三順位の方が亡くなっている時には「代襲相続人」として第一順位の子供は孫、第二順位の父母は祖父母、第三順位の兄弟姉妹は甥・姪が代わって相続します。
なお民法上で第一順位・第三順位の相続人には「代襲相続」と規定されていますが、直系尊属は民法上「代襲相続」と明記されていません。
ただし父母がいない時には祖父母、祖父母がいない時には曾祖父母とさかのぼり実質は代襲で相続します。父母は実父母に加え、養父母も含まれます。
なお子供と孫が両方いる場合には子供、父母と祖父母が両方いる場合には父母と被相続人に近い者が相続人となります。
2.代襲相続人が亡くなっている
被相続人の代襲相続人が亡くなっている場合は誰が相続人になるのでしょうか?
相続人が直系卑属(子供・孫)の場合は代襲相続に制限がなく、ひ孫が「再代襲相続人」となります。父母など直系尊属は上記の通りさかのぼって相続人を決定します。
相続人が兄弟姉妹で亡くなっている際には甥・姪が代襲相続人となります。ただし代襲相続は「甥・姪まで」と定められていますので、甥・姪が亡くなっている時にその子供が相続人になることはできません。
3.配偶者がいない又は亡くなっている
常に相続人である配偶者がいない又は亡くなっている時には、被相続人の血族である第一~第三順位全ての遺産を相続します。
4.身分関係が重複している
相続人同士の身分関係が重複した時には、2つの相続人の地位を引き継ぎ、相続分は合計します。
例えば祖父が孫を養子にし、孫が代襲相続人となったケースでは、孫は子(孫からみると親)の代襲相続人であり、被相続人の子ということになります。
孫の相続分は「養子分+代襲相続分」の合計です。
5.相続人の中に胎児・非嫡出子がいる
民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されていますので、相続の権利があります。未婚の男女の間に生まれた子供(非嫡出子)も同様に相続権を持っています。
死産になってしまった時には相続人ではないとみなされます。
6.相続放棄がある時
相続財産に債務が多い、財産を相続したくないケースでは相続開始から3ヶ月以内に被相続人の全ての遺産を放棄する「相続放棄」の手続きを行います。
相続放棄があった時には、最初から放棄した相続人はいなかった者としてみなされ、子や孫も代襲相続の権利を失います。
例えば第一順位の子供が相続放棄した場合、孫は代襲相続の権利を失い、父母の順位が上がり相続人となります。
他の相続人に影響を与える可能性がありますので、相続放棄は慎重に検討しましょう。
7.相続人がいない
相続人がいない時には、相続財産は国庫に帰属させることになります。
なお民法上相続人ではなくても生前相続人と親しかった方(特別縁故者)に相続財産が分与されることもあります。
特別縁故者や特定遺贈を受けた方などが家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立て、財産管理人が財産を管理します。
8.相続人の中に養子がいるとき
養子や結婚して嫁いだ子供にも相続の権利がありますが、「法定相続人」の数に含める養子の数は税法上一定数に制限されています。(被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、いない場合には2人まで)
法定相続人の数は、相続税の基礎控除額や総額に影響を及ぼし計算の結果が変わりますので注意しましょう。
特別養子縁組、配偶者の実の子供で被相続人の養子などのケースでは実の子供として取り扱われます。
9.相続廃除・欠格となる場合
相続廃除とは、相続人となる予定の方が被相続人を虐待した、重大な侮辱を与えた場合などに「廃除届」を提出し「相続人として認めない」とするものです。家庭裁判所に申し立て認められた場合に成立し、相続人の資格がなくなります。
相続欠格は遺言書を偽造・変造・隠匿した、詐欺や脅迫で遺言の取り消し・撤回をさせた、自身と同順位の相続人を殺害(未遂も含む)した等のケースで相続の権利を失います。
たとえ遺言書に相続する旨が書かれていても、相続は行われません。
相続欠格又は廃除により相続権を失っている場合、直系卑属(子供)が相続人である際は孫が代襲して相続人となり、相続人が兄弟姉妹の時は甥・姪が代襲相続人となります。
まとめ
民法で定められている相続順位・割合と遺産分配の決定方法、9つのケース別の相続について解説してきました。
法定相続分では配偶者・子供や父母、兄弟姉妹などに相続権があり、特に配偶者は被相続人亡き後の生活保障のために常に相続人となり相続分も多めに設定されています。
ただし各々の家庭によって事情が異なりますので、様々なケースについて理解しておくことも重要です。
この記事で遺産相続の順位・割合について理解し、スムーズな相続を行っていきましょう。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/