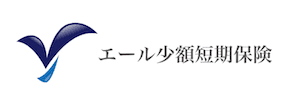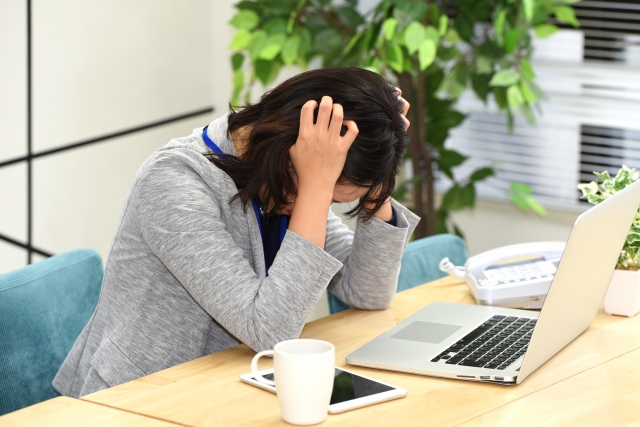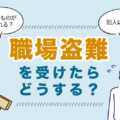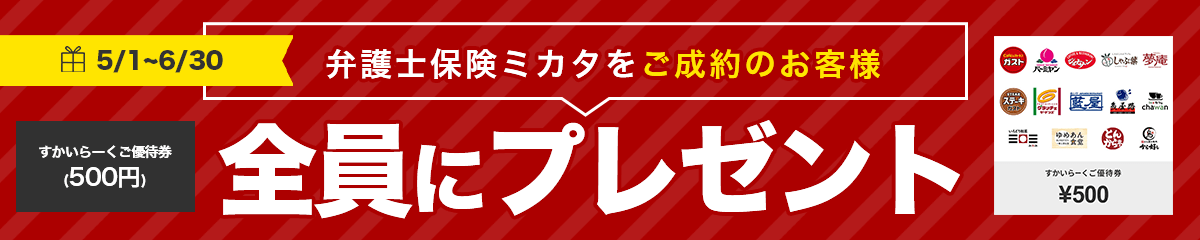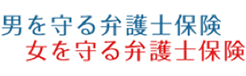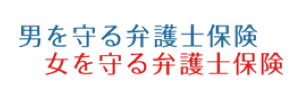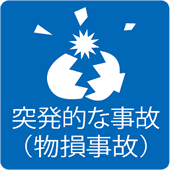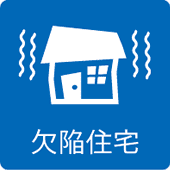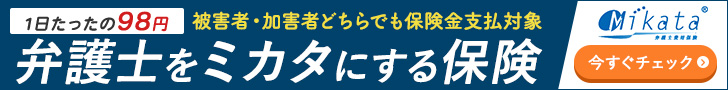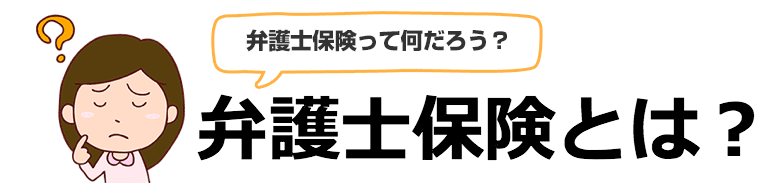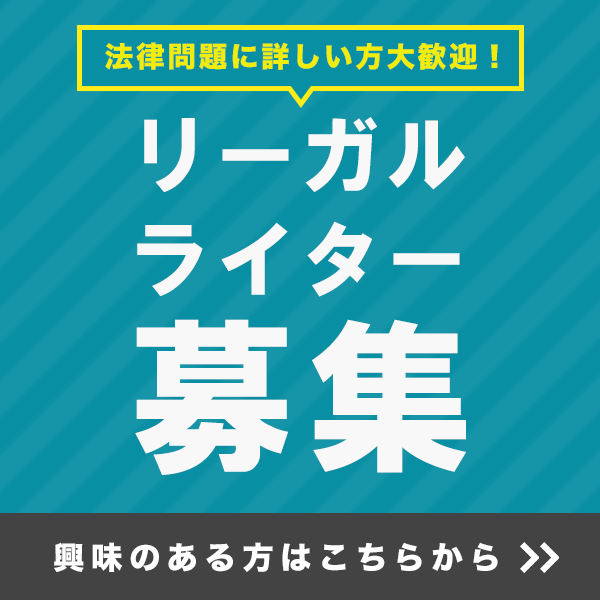給料が支払われない!相談先と請求方法は?
2020年04月3日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-
弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
給料が支払われなくて悩んでいる方は、早急に請求の手続きを進めてください。
未払いの給料の支払いには時効期間が設けられており、時効を過ぎると未払いとなっている給料は取り返せなくなってしまいます。
給与の未払いが起こった場合の相談先から請求方法まで詳しく紹介します。
給料の未払い問題はどこに相談すればいい?
給料が支払われなくて悩んでいる方は、「労働基準監督署」 「労働組合」 「弁護士」のいずれかに相談してください。
各相談先の特徴を紹介するので、自分にあった相談先を探してみてください。
労働基準監督署に相談
労働基準監督署とは、労働関係の法令違反を犯している企業を取り締まる機関です。
賃金の未払いは労働基準法違反であり、企業を取り締まるために労働基準監督署が対応してくれます。
電話、メール、窓口での相談が可能となっており、匿名での相談も可能です。
ただし、メールや電話での相談は緊急性が低いとみなされ、対応を後回しにされてしまうことがあるので注意が必要です。
スピィーディーな対応を望むなら、窓口で相談するのがベストです。
また、紹介したように、労働基準監督署はあくまでも法令違反を犯している企業を取り締まるための機関です。
そのため、賃金を支払うよう是正勧告は行ってくれますが、未払いとなっている賃金を取り戻しまでは対応してもらえないことがあります。
労働組合に相談
労働組合は労働者が自分たちの権利を守るためにつくる組織で、誰でも入会が可能です。
労働組合に加入していると団体で交渉が行えるうえに、問題を解決するためのアドバイスももらえます。
サポートしてくれる仲間がたくさんいるので、安心して問題解決に取り組めます。
また、労働組合との交渉を会社が拒否することはできないため、確実に交渉が行えるのは労働組合に加入する大きなメリットです。
個人で加盟できる労働組合もあるので、会社に労働組合がなくても全く問題はありません。
労働組合によって得意分野は異なるため、就業している業界や職種にあった労働組合に加入するようにしましょう。
労働組合は加入するメリットも多いですが、毎月の会費の支払いが必要で組合の活動に時間を拘束されるといったデメリットもあります。
メリットとデメリットを踏まえたうえで、労働組合への加入を検討していきましょう。
弁護士に相談
確実に未払いの給料を取り返したいなら、弁護士に相談するのが一番です。
個人で未払いの賃金を請求するとまともに会社が取り合ってくれないこともありますが、弁護士を立てれば会社も交渉をせざるを得なくなります。
また、未払いの給与を請求する際には必ず証拠が必要になりますが、弁護士に依頼すれば会社に対して開示請求が行えるので必要な証拠を入手しやすくなっています。
労働問題に強い弁護士であればこの手の問題には慣れており、効果的な方法でスピィーディーな解決が目指せます。
未払いとなっている給与に加え、支払いの遅延に伴って発生する遅延損害金も含めての回収が望めるのも嬉しいポイントです。
弁護士への依頼は高額な費用がネックという方も多いかもしれませんが、完全成功報酬型を採用している弁護士も多く相談料や着手金を支払わずに依頼できるケースもあります。
未払い給与の請求方法
未払いとなっている給料の請求は、自分で行えないわけではありません。
ただし、手続きが煩雑なため、弁護士など専門家に任せるのがおすすめです。
自分で請求を行う方法と弁護士に依頼して請求を行う方法を紹介するので、2つの方法を比較して自分にとって最適な方法で請求を行ってください。
自分で請求を行う場合
自分で請求を行う場合は、次の手順で請求を進めていきます。
証拠を集める
未払いの給与請求するためには、給与が支払われている事実を証明しなければいけません。
そのために、労働していたことを示す証拠が必要です。
タイムカードや業務日報、シフト表など、有効な証拠を集めてください。
未払いとなっている給与の金額を計算
タイムカードやシフトなどの証拠をもとに、未払いとなっている給与の金額を計算します。
内容証明を送付し時効を止める
未払い給与の請求は何年も遡って行えるものではありません。
実は未払い給与の請求には時効が定められており、時効期間は給与の支払日から2年となっています。
つまり、給与の支払日から2年を経過した分の給与については、取り返すことはできないということです。
損をすることがないように、内容証明を会社に送付して時効を停止させましょう。
内容証明により、半年間時効が止まります。
また、内容証明を送付したにも関わらず、内容証明は届いていないと会社に白を切られるケースもあります。
確実に内容証明を送付した事実を残すには、内容証明を配達した日付や宛名が証明される「配達証明」での送付がベストです。
会社と交渉する
会社と交渉を進めていきます。
ただし、給与の未払いを行うようなブラック企業は、まともに交渉を行ってくれないケースも多くなっています。
個人で交渉を行っても会社には脅威とならないため、交渉の場にさえついてもらえないこともあります。
また、交渉の場にはついてくれたとしても弁護士を介して減額交渉を行ってくることもあり、個人で満額を回収するのはなかなか厳しくなっています。
弁護士に依頼して請求を行う場合
弁護士に依頼する場合も、請求の手順として変わりはありません。
ただし、自分で請求を行う場合はすべての手続きを個人で行う必要がありましたが、弁護士に依頼する場合は弁護士がすべて行ってくれるので手間をかけずにスムーズに請求を進めていけます。
また、証拠がなくても相談に乗ってもらえるので、困っている方は一度相談してみると良いでしょう。
特に、給与の未払い問題においては、請求を免れるために会社がタイムカードなどの証拠を開示してもらえないことも珍しくありません。
交渉においても個人が行うのと法律の専門家である弁護士が行うのでは、会社へのプレッシャーも大きく変わり交渉を無視されるようなこともなくなります。
また、交渉が不発に終わっても、労働審判や裁判を行いしっかり問題解決に努めてもらえます。
弁護士がどのように交渉を進めていくのか紹介します。
交渉
まずは、弁護士が対面や電話、書面で、会社と直接交渉を行います。
交渉は全て弁護士が行うので、依頼者は特に何もする必要がありません。
会社の人と直接会う必要もないので、安心してください。また、交渉の開始時期は相談して決められます。
気まずくなるので在職中の交渉は避けたいとう方は、退職後に交渉を開始するように依頼しましょう。
労働審判
残念ながら交渉で合意に至らなかった場合は、労働審判に入ります。
労働審判とは、労働者と雇用者のトラブルを解決するための制度です。
労働審判は裁判所で行われ、裁判官、労働関係の専門家、申立人、相手方、代理人で審理を行っていきます。
労働審判は最大で3回行われますが、あなたが労働審判に参加する必要があるのは初回のみで2回目以降は参加する必要はありません。
労働審判は裁判に比べて期間が短いのが特徴で、スピーディーな解決が期待できます。
また、裁判ほど高額な費用がかからないのも、うれしいポイントです。
裁判
労働審判で解決に至らなかった場合は、裁判に入ります。
裁判は労働審判のように、回数制限が設けられていないため判決が出るまでに長い期間を要することがあります。
しかし、あなたが毎回裁判に行く必要はなく、本人尋問が必要な時だけ出廷すれば大丈夫です。
訴訟の流れとしては、訴状を提出してから地方裁判所での判決が出るまでに1~2年程度を要し、高等裁判所での判決には半年程度、最高裁判所で判決には3カ月~2年程度の期間が必要です。
ただし、最高裁判所までいくことはほとんどなく、地方裁判所で決着がつくことが多くなっています。
また、給与の未払い問題において裁判まで発展することは珍しく、交渉や労働審判の段階で解決できるケースが一般的となっています。
未払いの給与の請求には証拠が必須
未払い給与の請求方法でも少し触れましたが、給与を請求する際には労働の事実を証明する証拠が必ず必要です。
過去には証拠が不十分として、未払い給与の請求が認められなかった事例も存在します。
未払いの給与を取り戻せるよう、しっかり証拠を集めておきましょう。
証拠を集めるといっても、どのような証拠が有効となるのか知っていなければ証拠を集めることができません。
有効となる証拠を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
労働の事実を証明する証拠
労働していた事実を証明する証拠としては、次のようなものが有効になります。
| タイムカード |
| 業務日報 |
| メールの送信記録 |
| 会社のパソコンの利用履歴 |
| シフト表 |
| 給与明細 |
| 就業規則 |
| 雇用契約書 |
上記のものは労働を示す重要な証拠です。
ただし、会社が開示してくれないケースもあるので、可能であれば写真などを撮って保存しておくのがベストです。
紹介した証拠がなくても、あきらめる必要はありません。
関係者の証言や自身がつけた勤怠記録が、証拠として認められるケースもあります。
勤怠記録は、内容が詳細なほど有効性が高まります。
時間の記録は1分単位で行うのがベストです。
また、嘘が発覚した時点で証拠としての信用性は無くなってしまうので、正確に記録をつけることが大切です。
証拠がない場合の対処法
紹介したような証拠が手元になくても、会社が保管しているケースがあります。
会社が開示を拒んでも開示請求や証拠保全命令の申し立てを行い、証拠の開示や提出を行わせることが可能です。
給与の未払い問題は早急に対応しよう
給与が未払いになっている場合は、迅速に請求の手続きを進めて行く必要があります。
未払いの給与の支払いに2年の時効期間が設けられており、対応が後手に回ると大切な給与が取り返せなくなってしまいます。
自分一人では解決が難しい場合は、弁護士などに依頼し早急な解決を目指してください。
万が一のトラブルに備えて弁護士保険へ加入しておこう
賃金の未払いをはじめ不足のトラブルが起きた際は、弁護士に頼るのが一番です。
法律のプロである弁護士に依頼すれば、スムーズな対応で満足のいく結果が期待できます。
しかし、弁護士に依頼するとネックとなるのが高額な費用です。費用を気にして、弁護士への依頼に躊躇する人も多いのではないでしょうか。
費用を気にせず弁護士に依頼したいという方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
弁護士保険は、弁護士に依頼を行った際に必要となる弁護士費用を補填してくれる保険です。
保険料は会社によっても異なりますが、月額2,980円で加入できる弁護士保険もあります。
万が一のトラブルに備えて、弁護士保険へ加入してみてはいかがでしょうか。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
| 法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/